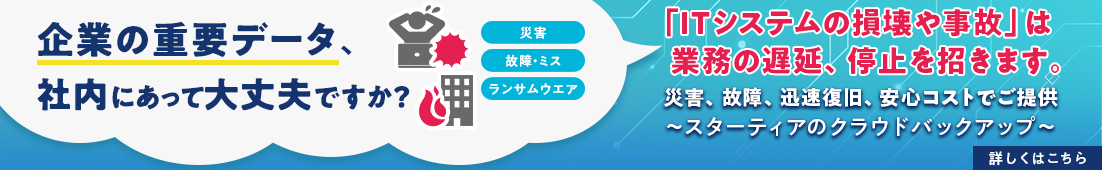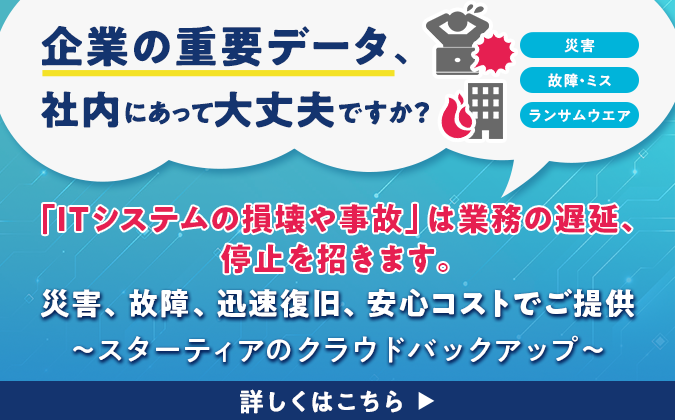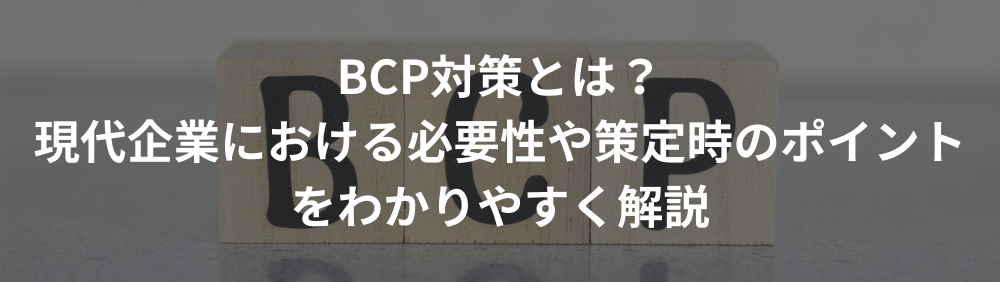
BCP対策は、さまざまな災害に対する備えとして必用といわれています。
ただし、具体的な策定方法がわからず、頭を悩ませているケースもあるでしょう。
そこで今回は、現代企業におけるBCP対策の必要性や、策定ポイントを業種別でご紹介します。
BCP(事業継続計画)とは
中小企業庁は、BCP対策を以下のように定義しています。
「BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです」
引用:中小企業BCP策定運用指針/中小企業庁
要約すると、BCPは自然災害・人的災害などに備えて平時に策定する計画であり、リスクマネジメントの一種といえます。
有事の際の行動指標にもなるため、あらかじめ策定し、社内全体に周知することが重要です。
ここでは、BCP対策の基礎知識や混同されやすいBCMおよび防災対策との違いを解説します。
BCMとの違い
BCPとBCMは、それぞれの言葉に含まれる意味の範囲が違います。
上記の通り、BCPは「Business Continuity Plan」を略した言葉、日本語では「事業継続計画」といいます。
これは自然災害やテロ、システム障害などの緊急事態が発生した際に、企業が事業を継続し、損害を最小限に抑えるためのものです。
自然災害を念頭に置きますが、感染症の流行や情報漏えい事故、国家間の紛争など、多種多様なリスクに対応するための包括的な対策を含みます。
一方、BCMは「Business Continuity Management」の略語であり、「事業継続マネジメント」を意味する言葉です。
緊急事態発生時の対処行動や復旧対応マニュアルなどの事後対策、組織内での意識啓発や訓練を含む一連のマネジメント活動を指すもので、BCMとは明確な違いがあります。
防災対策との違い
BCPと防災対策との大きな違いは、対策時に意識する目的の差です。
BCPは「事業継続計画」の意味通り、緊急時における事業の復旧・存続を策定目的とします。
対して防災対策は、主に自然災害から生命・住まい・資産などを守る目的があります。
具体的には、避難訓練や建物の耐震強化、防災グッズの準備などが挙げられます。
BCPは広義における「災害」に備える一方で、防災対策は原則、自然災害にフォーカスしているのが特徴といえるでしょう。
BCP対策が重要視されている理由
国内外で多発する自然災害や感染症リスクの影響から、近年はBCP対策の重要性が高まっています。
ここでは、なぜBCP対策が重要なのか、複数の観点から深掘りします。
自然災害の増加
2000年以降、国内外で大規模な地震・台風・水害が発生し、企業におけるBCP対策の必要性が一層強調されています。
特に注意したいのが、自然災害がもたらす「二次災害」です。
たとえば、地震による被害でオフィスが半壊し、インターネットや固定電話が使えなくなったとします。
社員や取引先に連絡を取れなかったり、サプライチェーンが途絶したりして、業務は完全に停止します。
こうした二次被害のリスクに対応するための「備え」は、現代企業にとって必要不可欠です。
感染症リスクの高まり
2019年末に起きた新型コロナウイルスによるパンデミックは、企業にとって未曽有の事態でした。
その影響は計り知れず、世界中の国・地域で経済活動が停滞したのは記憶に新しいところです。
これを機に、企業におけるBCP対策の重要性が浮き彫りとなりました。
以降、BCPには自然災害だけでなく、感染症のような公衆衛生危機にも対応するリスクマネジメントが盛り込まれるようになりました。
デジタル化の進展
システム障害やサイバー攻撃により社内情報が流出し、大規模な情報漏洩事件へと発展するケースが起きています。
とりわけ近年は、パンデミックの影響で働き方が多様化しました。
テレワークなどを機に、従業員のPCから顧客情報などが漏洩した事例があります。
こうした情報セキュリティ上の観点から、BCP対策を策定し、デジタル資産の保護や業務継続性の確保を進める動きが見られます。
社会的要請の高まり
国や政府、ひいては社会全体がリスクマネジメントを「企業の社会的責任」と捉えるようになりました。
災害発生時も事業を継続できるとわかれば、取引先からの信頼感は向上するでしょう。
ただ、BPC対策が国内企業に浸透しているかというと、不十分な印象は拭えません。
「令和4年版 防災白書」によると、日本国内のBCP策定率は、大企業で70.8%、中堅企業で40.2%とのことです。
自然災害やパンデミックの発生など、未曾有の事態が起きているにもかかわらず、その危機管理意識は今ひとつといえます。
社会的要請が高まっている今、できるだけ早く自社のBCPを策定すべきでしょう。
引用:令和4年版 防災白書|大企業と中堅企業のBCP策定状況
BCPの策定手順
実際にBCP対策を策定する際は、以下のBCPガイドラインをもとに策定するのがおすすめです。
ここでは、「中小企業BCP策定運用指針」の内容をもとに、中小企業庁が推奨するBCPの策定手順をご紹介します。
引用:中小企業BCP策定運用指針
STEP1.BCPの目的を決める
BCPを策定するとき、まず着手するのは当該計画の目的を決めることです。
事業継続のために何を守るべきかBCPで明確に示されると、従業員はその方針に沿って、適切に動きやすくなるためです。
企業が掲げる目的の骨子としては、「従業員や顧客を守るため」や「取引先からの信用を守るため」が適しているとされます。
これらの内容を自社の経営理念や運営方針と照らし合わせ、BCPの目的を定めます。
このように、災害発生時は何を優先的に守るか、明確に示すことが大切です。
STEP2.重要業務とリスクを整理する
BCP策定の第2段階では、自社における重要業務と災害時のリスクを整理します。
まず、自社において最も優先すべき事業を「中核事業」に指定します。
これには「売上の多い事業」や「企業の信用に関わる事業」が相当するでしょう。
また、災害発生により想定される状況のうち、事業継続に影響のあるリスクも一通り洗い出します。
ここで検討したいリスクは、自然災害・感染症の流行やサイバー攻撃が事業に及ぼす影響と危険性です。
災害時に危惧される多様なリスクを明確化しておけば、リスク回避に有効な対策・対処法を検討しやすくなります。
STEP3.リスクに優先順位をつける
事業継承に対するリスクを洗い出したら、次は各リスクに優先順位をつける工程に着手します。
上記の通り、災害発生時は多種多様なリスクが生じ、業務遂行な困難になるケースも少なくありません。
とはいえ、すべてのリスクに対策することは困難です。
発生したリスクに対し、どこまで対処できるか実現性を考慮した上で、優先順位を決めましょう。
リスクの優先順位を決める判断基準は、その影響度と発生確率にあります。
事業継続に深刻な影響があり、なおかつ頻繁に起きるリスクは、早急な対策が必要でしょう。
おのずと優先順位が上がり、自社にとって脅威であると判断できます。
いずれにしても、あらゆる事態を想定し、優先順位の高いリスクに備えることが大切です。
STEP4.リスクごとに対応策を決める
続いて、リスクごとにBCPの具体的な対応策を決めるプロセスに入ります。
具体的には、緊急時にトップの立場で指揮する人物を明示し、誰が何を実行に移すなど、細かく割り振っていきます。
個々の役割が明確になっているほど、緊急時の対応はスムーズになるためです。
ただし、ひとつの行動パターンしか策定しないと、さまざまな危機的状況に対処することは難しくなるでしょう。
いずれの状況下でも適切な行動を取るには、リスクごとに、事前対策や災害発生時の初動対応、事業復旧の手順などを具体的に定める必要があります。
また、現実味のない対応策は実効性が期待できません。
対応策はあくまでも、現実的に実行可能な内容にしましょう。
STEP5.発動体制や基準を決める
最後に、BCPの発動体制や発動基準を決めます。
これらの項目をはっきり定めると、有事の際に、適切なタイミングと体制で、緊急対応を開始できるでしょう。
発動体制や発動基準が明確であれば、トップダウンの素早い緊急対応につながり、被害の拡大防止や事業の早期復旧がスムーズになります。
以上の手順で具体的・現実的なBCPを策定すれば、災害発生時の冷静かつ適切な判断・行動が可能になるでしょう。
企業がBCPを策定する5つのメリット

企業がBCPを策定するメリットとして、リスク管理や企業価値の向上などが挙げられます。
ここでは、BCP策定前に知っておきたい5つのメリットを解説します。
リスクマネジメントになる
BCPは、災害発生におけるリスクマネジメントになります。
あらかじめ緊急時の対応策を検討していない場合、速やかな対応は難しくなるでしょう。
天災・人災が起きたとき、緊急対応に手間取ると、被害は拡大し、事業再開までに時間とコストを要します。
一方、事前の備えが整っている場合、大規模災害に見舞われても速やかに緊急対応を開始できます。
BCPによって甚大な被害を受けるリスクが軽減され、短時間で事業を復旧しやすくなるでしょう。
企業価値の向上
BCPの策定は、取引市場や地域社会における企業価値の向上に繋がります。
災害発生時、企業が速やかに事業を復旧・継続できれば、市場や地域全体における経済活動の停滞に歯止めがかかります。
というのも、企業は大規模災害発生時、自社事業を素早く復旧・存続することが、一種の社会貢献になるのです。
たとえば、食品メーカーや運送業は、自社の事業を維持できれば、飲料や食料品の生産・供給を続けられるでしょう。
これらの業種はインフラ的な役割も担うため、事業継続が人々の生活に与える影響は大きくなります。
したがって、BCPを策定すれば「有事に備えている企業」というイメージがつき、結果的に企業価値が向上しやすいと考えられます。
事業継続能力を確保できる
企業が事業継続能力を確保できる点も、BCPを策定するメリットです。
有事の際、危機管理能力が乏しいと、災害時による被害が拡大する傾向にあります。
「災害大国」と呼ばれる日本の企業は、できるだけ早くBCP対策を策定すべきでしょう。
公的支援を受けやすくなる
行政はBCPを策定した企業に向けて、さまざまな公的支援制度を設けています。
BCP策定に取り組むことで、補助金の支給や税制優遇、金融支援を受けられるのが魅力です。
それだけ国・行政においても、国内企業のBCP策定率を高めようと取り組んでいるわけです。
速やかな事業復旧・存続を遂げるには、たとえ被害が小さくても、相応の資金を投じる必要があります。
BCP策定によって公的支援を受けられるのは、中小企業をはじめ、大きなメリットといえるでしょう。
倒産や顧客離れのリスクを軽減できる
近年、消費者の間では、企業側の社会貢献を期待する声が高まってきました。
多くの企業は、自社の利益を追求するだけでなく、社会的な責任を果たす姿勢も求められています。
BCPの策定で災害発生時の早期復旧が可能になれば、倒産するリスクを減らせるでしょう。
また、事業継続により社会貢献を果たせば企業価値が見直され、顧客離れのリスクも軽減できると考えます。
BCP策定時の注意点
企業でBCPを策定するときは、実現可能性を念頭に置くことが大切です。
どれほど綿密な計画を立てても、現実的でない内容は実行に移せません。
有事の際にBCPが機能せず、計画倒れになる事態を避けるには、現実的かつ遂行可能な対応策を盛り込む必要があります。
また、事前にシミュレーションを実施し、BCP自体の精度を高めることも重要です。
試験的な運用を通じて課題を洗い出し、内容をブラッシュアップしていきましょう。
【業種別】BCP対策の策定ポイント
ここでは、製造業・販売業・運輸業におけるBCPの策定ポイントをご紹介します。
製造業の場合
製造業におけるBCP対策の策定ポイントとしては、人命の安全を最優先にし、安否確認の手法を事前に決めておくことです。
たとえば、防災対策として施設内の危険箇所の把握、商品や資材の転倒・落下防止、サーバーやOA機器の固定、ガラス類の飛散防止、備蓄などが挙げられます。
また、代替生産できる事業継続体制を整えることも重要です。
大手メーカーの場合は、調達先の分散化やサプライヤーへのBCP導入の指導がポイントになります。
製造業は災害発生時に業務が停まると、あらゆる業種・職種に影響をおよぼします。
自社がインフラとして機能することを認識し、社会や取引先への影響まで考慮したBCP対策が必要となるでしょう。
小売業の場合
小売業のBCP対策では、来店客の安全確保が最優先事項です。
たとえば、大規模な地震が発生した際、出入り口付近での混乱を避けるために、来店客を複数の非常口に分散させるように声をかけます。
従業員を非常口付近などに配置し、緊急時の誘導を行うのもポイントです。
さらに災備蓄品の点検や避難訓練を定期的に行い、緊急時にも冷静に対応できるように備えましょう。
また、小売業においては、販売チャネルの多様化も重要といえます。
オンラインストアの開設や電話での注文受付、自動販売機の設置など、災害発生時も顧客に商品を提供できる仕組みを用意します。
運輸業の場合
運輸業におけるBCP対策は、予期せぬ事態に備えて物流機能を維持し、早期に復旧するための体制を整えることが優先です。
ポイントは、荷主と物流事業者の連携にあります。
まず、防災対策として、事業所や施設の危険度をハザードマップで把握し、必要に応じて耐震・遮水・荷崩れ防止などの対策を実施します。
また、通信手段の多重化やデータのバックアップ、重要代替拠点・設備の確保なども行いましょう。
発災直後の措置として、人命を最優先に守るための基準を定め、スタッフが冷静に行動できるようにします。
これには、行動マニュアルの作成や想定される被害への対応に関する協議が含まれます。
復旧対策の実行では、事業の早期復旧を目指し、サプライチェーンの維持に必要な施設や輸送力の確保、代替輸送・施設・作業のスキーム構築などを行います。
そして平時からの準備として、BCP担当者の育成や配置、社内教育体制の充実、訓練の徹底などを行い、万が一の時に素早く行動できるようにします。
いずれも自然災害やシステム障害などの不測の事態に対応し、物流を止めることなく維続できる体制の構築に不可欠です。
まとめ
BCP対策は、有事の際に事業を継続させるための計画であり、行動指標です。
昨今は、自然災害の増加から、企業におけるBCP対策の重要性が高まっています。
これは単なる「備え」ではなく、社会的信頼や企業価値に影響する要因でもあります。
本記事や中小企業庁のWebサイトを参考に、BCP対策の策定に取り組んでみましょう。
▽関連記事▽
UTM(総合脅威管理)とは?主要機能や企業における導入メリット
サプライチェーン攻撃をわかりやすく解説!主な手口や被害事例は?
おすすめ資料ランキング





【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-