中小企業向けDX特集⑰DX推進の第一歩はペーパーレス化!メリット・デメリットや進め方について解説 (ペーパーレス化 進め方)
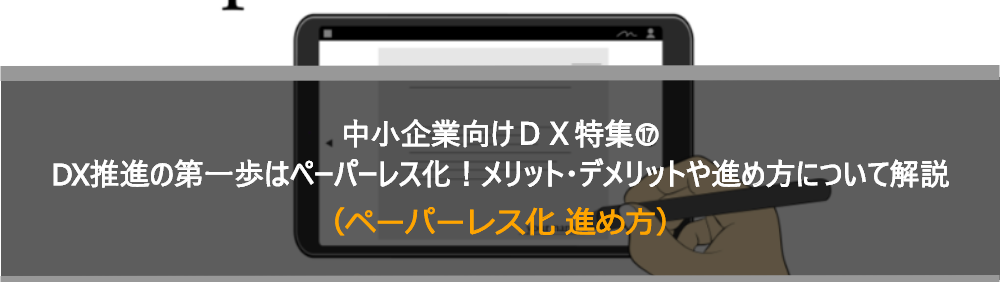
DXという言葉が注目されるようになり、テレビやインターネットで目にする機会も増えています。
何か自社でも取り組まなければと考えている中小企業の経営者の方も増えているようですが、
何をして良いかわからないという場合も多いのではないでしょうか。そんな企業にお勧めしたいのが「ペーパーレス化」です。
今回は、DX推進の第一歩ともいえるペーパーレス化のメリット・デメリットや進め方について解説します。
1. ペーパーレス化の概要と現状
1-1 ペーパーレス化とは?
ペーパーレス化とは、紙媒体を可能な限り電子化(デジタル化)し、データとして保存・活用することです。
ビジネス上で使用する紙資料の他、本や雑誌を電子書籍化したり、
チケットを電子チケット化したりといったこともペーパーレス化の一つです。
1-2 ペーパーレス化の現状
日本でなかなかペーパーレス化が進まなかった理由の一つに、
法律で紙による保存を義務付けられた書類が多かったことがあげられます。
しかし、「e-文書法(電子文書法)」や「電子帳簿保存法」の規制緩和によってその状況は改善されており、
国としてもペーパーレス化を後押しする形になっています。それぞれの法律について簡単にご紹介しておきましょう。
「e-文書法(電子文書法)」とは2005年4月に施行された法律で、この法律により、法人税法や商法、
証券取引法などで紙による原本保存が義務付けられていた文書や帳票を電子データで保存できるようになりました。
「電子帳簿保存法」とは1998年7月に、国税関係および電子取引に関する書類を対象として施行された法律です。
これが2020年4月に改正され、スキャナ保存の要件が追加されたことでペーパーレス化がしやすくなりました。
これ以外にも、想定外にペーパーレス化を押し進める要因となったのが、新型コロナウイルスの感染拡大です。
感染拡大を防止するためにテレワークの実施が求められたことにより、
ペーパーレス化をせざるを得なくなった企業が増加したのです。
ペーパーレス化は自社だけが行っても、取引先がアナログなままであると不便を感じることもあり、
業界全体で推進されることが望ましいのですが、なかなか足並みが揃わずにいる業界がほとんどでした。
しかし今回この新型コロナウイルスの影響により、日本全体が同時に同じ状況に置かれたことも期せずして追い風となったのです。
さらに、押印のために出社しなければならない社員がいたことが問題となったこともあり、
電子契約の整備も一気に進みました。これにより、さらにペーパーレス化がしやすい環境となっています。
このような状況下においてペーパーレス化を進めないことはむしろリスクとなる可能性があり、
生産性とスピードの面で大きく立ち遅れないように、早めに取り組みをスタートすることが望ましいといえます。
2. ペーパーレス化を進めることのメリット
2-1 コスト削減につながる
ペーパーレス化を進めることで最も感じやすいメリットはコストの削減です。
例えば、ペーパーレス化をすると、これまで会議の度に人数分用意していた分厚い資料の印刷が不要になります。
用紙代はもちろんのこと、印刷費用も削減できるので、
カラーコピーを多用していた企業であれば特に、大きなコストの削減になるでしょう。
それ以外に、請求書や契約書などの印刷コストについても、積み重なれば大きなコスト削減になります。
また印刷コスト以外にも、取引先へ郵送するための封筒代や郵送代の削減にもつながります。
そして意外と意識されないのが人件費です。
プリントアウトやファイリング作業には人件費がかかっていますから、これを削減することができるのです。
2-2 業務効率化につながる
ペーパーレス化による最も大きな価値は、業務効率化ではないでしょうか。
業務効率化によって生まれた時間で働き方改革を進めたり、コア業務に力を入れたりすることで、生産性も高まるでしょう。
具体的な例は以下の通りです。
・印刷、製本が不要になる
・データの検索が簡単に早くできる
・各種届け出が簡単に早くできる
・他社とのやり取りが簡単に早くできる
2-3 ミス削減につながる
経理関連でペーパーレス化が進めば、請求書の発行漏れや清算漏れといったミスの削減につながります。
2-4 紙資料の保管場所が不要になる
紙資料の保管場所が不要になることでオフィスの省スペース化を実現できます。
空いたスペースを有効活用することができれば、生産性を高められるでしょう。
ペーパーレス化とリモートワーク推進でより小さなオフィスへの移転が可能になれば、
オフィスコストの削減につながる可能性もあります。
その他、キャビネットなどを購入する費用や管理コストも削減できます。
2-5 データのバックアップと複製がしやすい
紙資料の場合、それ自体が紛失したり破損したりしてしまうと復元することは難しいです。
しかし、ペーパーレス化をしていればサーバーでデータのバックアップをとることができるので、複製や復元も簡単にできます。
2-6 書類情報が簡単に共有でき、情報の属人化を防げる
ペーパーレス化により様々な書類情報がデータ化され、クラウドなどに保存されていれば、
誰もがその情報に即座にアクセスすることができるので、情報の属人化を防ぐことができます。
2-7 セキュリテイの強化が図れる
紙の書類は、その量が増えれば増えるほど紛失に気がつかず、
知らない間に情報が漏洩してしまっているといったことが起こり得ます。
ペーパーレス化をしておけば、そのようなリスクが回避できるでしょう。
もちろん、データ化された情報も紛失や漏洩のリスクがありますが、
データを消したりコピーしたりすればログが残りますし、
アクセス権限のコントロールもできるので、セキュリティの強化が図れます。
2-8 リモートワークを円滑に進められる
ペーパーレス化をすると、書類管理をオンラインで行うことができるようになります。
オフィス以外にいても、いつでも必要な書類にアクセスできるようになれば、リモートワークを円滑に進めることができます。
リモートワークではオンライン会議も実施することになりますが、
対面会議の時のように紙資料を印刷して自宅などに郵送するのは現実的ではありません。
パソコン上で資料を共有したり、タブレット端末を配布してそこから確認をしたりすることで、スムーズに進めることができるでしょう。
2-9 SDGsの取り組みにつながる
ペーパーレス化は、SDGsなどの地球環境保護の取り組みにつながります。
SDGsに取り組んでいるかどうかが企業の評価につながる時代ですので、そうした面でもペーパーレス化はメリットになるでしょう。
3. ペーパーレス化を進めることのデメリット
3-1 導入・運用コストがかかる
ペーパーレス化で最も気になるデメリットは、導入・運用コストでしょう。
PC・タブレットなどの端末を購入したり、システムの導入やサーバー・インフラなどの環境を整備したり、
クラウドサービスなどの利用費用を毎月支払ったりといった費用がどうしてもかかってしまいます。
長期的な視点で考えるとコスト削減になり、業務効率化という大きなメリットもあるのですが、
初期費用の準備が難しいとペーパーレス化の大きな障壁となってしまいます。
3-2 一定のITリテラシーが必要
クラウドサービスの利用、各種システムの活用など、ペーパーレス化を進めると一定のITリテラシーが必要な作業が増えます。
ベテラン社員が多い企業などでは、タブレット端末の操作などに慣れていない人間が多く、
紙の資料からの移行に抵抗を覚える方もいるでしょう。
できるだけ直感的に扱えるようなシステムを選ぶ、わかりやすいマニュアルを作成する、導入研修を行うなどの対応が必要です。
3-3 ITツールやサービスの障害やセキュリティのリスク
ITツールやサービスに障害が起こってしまった時に、業務が停止してしまうリスクがあります。
こうした場合に備えて、バックアップ体制を整えておく必要があるでしょう。
オンライン上でデータのやりとりをするからこそのセキュリティリスクもあります。
セキュリティに関する知識を持ち、ある程度費用と手間をかけてでもしっかりと対策をする必要があるでしょう。
3-4 慣れるまで業務効率が下がる可能性がある
一定のITリテラシーがある方であっても、ペーパーレス化によって仕事の進め方が変われば、慣れるのにある程度時間がかかるでしょう。
新しい運用方法が定着するまでの間は、業務効率が下がる期間が生まれてしまう可能性があります。
4. ペーパーレス化の進め方
4-1 ペーパーレス化の進め方①ペーパーレス化のメリットを従業員に認識させる
これまでのやり方を変えることに抵抗を感じる従業員の方は必ずといっていいほど出てきます。
まずはペーパーレス化のメリットを従業員に認識させることが必要です。
そのためには、経営者がメリットを十分に理解し、積極的に発信していくことが求められます。
また従業員の年齢層が高い企業では、スマートフォンやタブレット端末に抵抗がある社員も多いので、
こうした端末を導入して慣れてもらっておくと良いでしょう。
ITツールについても抵抗のある人がいると思いますので、マニュアルの作成や研修も行う必要があります。
4-2 ペーパーレス化の進め方②デジタル化する書類選択と優先順位を付ける
ペーパレス化といっても、ありとあらゆる紙をデジタル化するわけではありません。
ルール上の問題によって紙保存しなければならないものや、
取引先との関係で紙保存が必要なもの、効率を考えると紙資料の方が良いものもあります。
まずは最終的にどの書類をデジタル化する必要があるのかを決め、その中で優先順位をつけていきましょう。
一度にペーパレス化を進めてしまうと、混乱を招く可能性もあります。
会議資料のデジタル化から進めるなど、ハードルの低いところから取り組むというのも、一つの方法です。
4-3 ペーパーレス化の進め方③デジタル化したデータの運用方法を決める
ただ紙媒体をデジタル化するだけでは、ペーパーレス化の価値を最大限に活かすことはできません。
デジタル化したデータをどのように運用するのかも重要なポイントです。
データの運用方法については、できるだけシンプルで誰にでもわかりやすい内容を心がけましょう。
4-4 ペーパーレス化の進め方④ペーパーレス化に使用するITツール等を選択する
ペーパーレス化した後の運用がスムーズに行くかどうかは、ITツールの選択に左右されます。
クラウドストレージや情報共有ツールなどのデジタルツールを、
文書サイズや使用感にあわせて最適なものを選択するようにしましょう。
ITツールに不慣れな方が多い会社では、できるだけシンプルで直感的に使用できるものを選ぶことをお勧めします。
4-5 ペーパーレス化の進め方⑤取引先に自社のペーパーレス運用に関して周知する
請求書や契約書、商談の際の資料などのペーパーレス化を進める場合、
自社だけの話ではなくなり、取引先にもこれまでのやり方を変更していただく必要が出てきます。
まずは自社がペーパーレス運用を始めたことを伝えるとともに、協力をしていただけるかを確認しなければなりません。
業務効率化を考えると、すべての取引先とペーパーレスで取引できるのが理想ですが、なかなかそうはいきません。
少しずつでもペーパーレス運用ができる企業を増やし、
自社だけでなく業界全体でのペーパーレス化、業務効率化を進められるように努めましょう。
4-6 ペーパーレス化の進め方⑤運用開始に加え、過去資料のデジタル化も進める
ペーパーレスでの運用を始めるとともに、過去の資料のデジタル化も進めていきましょう。
大変な作業ではありますが、過去のデータをデジタル化することで紙書類の保管場所が不要になるだけでなく、
これまでに蓄積されたデータを分析して経営に活かしたり、情報の検索を容易にしたりと大きなメリットにつながります。
5. まとめ
ペーパーレス化には初期費用や運用費用がかかるものの、
長い目で見た時のコスト削減や業務効率化など大きなメリットがたくさんあります。
国としてもペーパーレス化を推し進めていることに加え、新型コロナウイルスの影響がさらに後押しとなり、
多くの企業でペーパーレス化の取り組みが始まっています。もしこのままペーパーレス化に取り組まなければ、
多くのメリットを享受できないだけなく、成長の機会を失う可能性もあるでしょう。
なかなか一歩を踏み出せなかった企業も、今がその一歩を踏み出すチャンスなのではないでしょうか。
おすすめ資料ランキング





【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-





















