中小企業向けDX特集⑯DX税制にも関連!DX推進や中小企業の成長を後押しする産業競争力強化法について解説 (産業競争力強化法 DX)
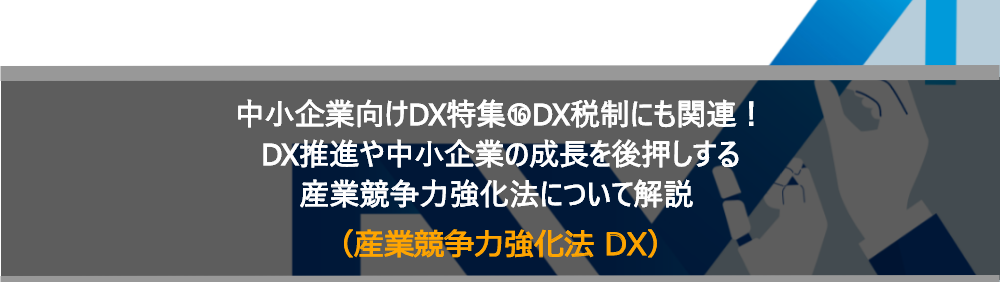
産業競争力強化法は、日本経済の再興のための産業競争力の強化を目的として、
2014年1月20日に施行された法律です。そして2021年8月2日に改正産業競争力強化法が施行され、
その中にはDX推進を強力に後押しする内容が盛り込まれました。中小企業の経営者にとっても
大きなメリットであるDX投資促進税制の適用の前提となるこの法律について、
DX推進に関連するポイントを中心に、取り組み事例や申請方法と併せてご紹介します。
1. 産業競争力強化法のDX推進に活かせるポイント
産業競争力の強化を目的として施行された産業競争力強化法ですが、
2021年8月2日の改正によりDX推進を後押しする内容が盛り込まれました。
改正によって、中小企業がDX推進に活かせるポイントは『「デジタル化」への対応』と
『「新たな日常」に向けた事業再構築』
の2つです。そしておさえておかなければいけない最も重要なポイントは、
この法律がDX投資促進税制等の適用の前提となることです。DXを推進するにあたって
予算の捻出は頭の痛い問題だと思いますが、DX投資促進税制のような税優遇は大きなサポートになります。
こうした税優遇の適用を受けるためには、事業適応計画の認定が必要です。
DXに関連する事業適応計画は①成長発展事業適応と②情報技術事業適応です。
それぞれについて、簡単にご説明しましょう。
①成長発展事業適応
経済産業省が発表している資料によると
デジタルトランスフォーメーション、事業再構築・再編等に向けた投資を行い、
経営改革に果敢に取り組むこと。
とされています。
DXに関しては、新型コロナの影響などで経営が悪化している中でも、デジタルトランスフォーメーション(DX)への
投資や取り組みを果敢に行なっている企業が認定の対象となります。
②情報技術事業適応
経済産業省が発表している資料によると
Digital Disruptionの動きに対応していくべく、
デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革(DX)に取り組むこと
とされています。
Digital Disruption(デジタル・ディスラプション)とは、デジタル技術によって既にある事業・産業を根底からゆるがし、
崩壊させてしまうような革新的なイノベーションのことです。
「情報技術事業適応」は、まさに企業が今の時代に適応していくために必要なDXへの取り組みを推進するものであるといえます。
2. 産業競争力強化法はDX推進や中小企業の成長にどんなメリットがある?
中小企業の経営者として最も気になるのは、産業競争力強化法(特に今回の改正内容について)には、
一体どんなメリットがあるのか?ということでしょう。
DX化の障壁となりやすい予算面のサポートにも関連しますので、ぜひ参考にしてみてください。
2-1 税優遇のメリット(DX税制)
産業競争力強化法の最も大きなメリットは、DX税制などの税優遇の適用が受けられることでしょう。
改正ポイントである『「デジタル化」への対応』では、DXを推進する企業への支援が行われます。
最もDXと関連性が深い税優遇は「DX税制(DX投資促進税制)」で、
他に越欠損金の控除の上限を最大5年間にわたり現行の50%から最大100%に引き上げるという措置も盛り込まれています。
「DX税制(DX投資促進税制)」については、下記をご確認ください。
<DX投資促進税制>
*対象税
所得税・法人税・法人住民税・事業税
*対象設備
①ソフトウェア
②繰延資産(クラウドシステムへの移行にかかわる初期費用)
③器具備品(①②と連携するもの限定)
④機械装置(①②と連携するもの限定)
*優遇措置
税額控除か特別償却を選択可能です。
・税額控除の場合
3%の税額控除
5%の税額控除(グループ外の他法人ともデータ連携・共有する場合)
※税額控除上限:「カーボンニュートラル投資促進税制」と合わせて当期法人税額の20%まで
・特別償却の場合
30%の特別償却
*投資額
上限:300億円
下限:売上高比0.1%以上
*適用期限
2022年度末まで(2023年3月末)
2-2 指定金融機関による長期・低利の大規模融資(ツーステップローン)
今回の改正では、財政投融資を原資とした低利融資も行われます。これをツーステップローンといいます。
産業競争力強化法におけるツーステップローンとは、日本政策金融金庫と指定の金融金庫を通じて、
事業適応計画の認定を受けた事業者に対し、認定された政策実施のために必要な資金の貸し付けを
国から受けられる仕組みです。融資の判断には、指定金融機関による審査が必要です。
融資期間は5年以上で、金額規模は50億円以上となっています。
2-3 ベンチャー企業やスタートアップ企業の再挑戦を支援してくれる
新型コロナの影響などによって事業継続が困難になったベンチャー企業やスタートアップ企業に対し、
独立行政法人中小企業基盤整備機構が資金調達の円滑化や有望資産の再活用によって再挑戦の支援をしてくれる制度です。
有望資産とは技術や人材などを指しており、事業継続が難しくなった企業から別企業へ
それらを継承する手助けをすることで、将来性のある技術や人材の活躍の場が失われてしまうことを防いでくれます。
この制度は、「ベンチャーリブート」と呼ばれます。
3. 中小企業の産業競争力強化法のDX化に関する取り組み例
改正後の産業競争力強化法は、強くDXを後押しする内容となっています。
改正によって、中小企業がDX推進に活かせるポイントは『「デジタル化」への対応』と『「新たな日常」に
向けた事業再構築』の2つであるとご紹介しましたが、この章ではそれぞれについてのDX化に関する取り組み例をご紹介します。
3-1 「デジタル化(DX化)」への対応
「デジタル化(DX化)」への対応とは、そのままDX化のことであると捉えられ、幅広い産業で取り組みが進んでいます。
例えば、経済産業省が公開している資料には以下の取り組み例が紹介されています。
顧客データを活用した販促情報の提供や無人決済の実現により顧客利便性を向上。
そのほか、DX化に関する過去の取り組み例をご紹介します。
・店頭で陳列する商品の棚札の電子化
価格の変更や陳列商品の変更のたびに棚札の交換をする必要がなくなり、
業務効率化ができたことで顧客サービスの質を高められました。
・不動産会社のオンライン内見
新型コロナにより活用事例が増えましたが、もともとは忙しくて内覧の時間が取れない方に向けたサービスとして、
VRクラウドソフトを使ってブラウザ上から賃貸物件のパノラマ画像を閲覧できるオンライン内見がスタートしました。
現地に行かなくても、どこからでも内見ができるという新しい価値を生み出した取り組みです。
3-2 「新たな日常」に向けた事業再構築
「新たな日常」に向けた事業再構築については、主に新型コロナの影響により厳しい状況に置かれている企業が、
生き残りをかけて事業の変革をおこなった取り組みがあげられます。
例えば、経済産業省が公開している資料には以下の取り組み例が紹介されています。
商品を自動判別・自動精算する無人店舗技術を持つ企業に出資し、
対面を前提としない店舗開発により生産性を向上。
その他、「新たな日常」に向けたDX化に関する過去の取り組み例をご紹介します。
・モバイルオーダーシステムの活用
新型コロナの影響で飲食店ではテイクアウトやデリバリーが盛んになっていますが、
それ以外にも注目されたのがモバイルオーダーシステムの活用です。スマートフォンで注文・決済を
完了させられるこのシステムは、店員と顧客の接触機会を減らし感染防止や業務の効率化をはかるだけでなく、
顧客はゆっくりと商品を選ぶことができる上に待ち時間を短縮できるという価値が生まれました。
・スマートチェックインシステム
新型コロナの影響で飲食店と並んで大打撃を受けた宿泊業界。旅館やホテルの部屋に入ってしまえば
ソーシャルディスタンスが保てるものの、チェックインまでの列やロビーが密状態になってしまい、
感染対策の面でも、利便性の面でも課題がありました。
それに対して、スマートフォンを見せるだけでチェックインができるシステムが開発されています。
4. 産業競争力強化法の事業適応計画(DX税制関連)で認定を受けるには?
認定を受けるには、事業者が事業適応計画を作成し、その計画にかかわる事業の分野を
所管する官庁へ認定申請をする必要があります。申請はオンラインで受け付けられます。
申請は一括して受け付けてもらえるので、あらかじめ所管大臣を特定する必要はありませんが、事業分野を特定は必要です。
この章では、申請手続きのスケジュールやフローをご紹介しましょう。
4-1 事業適応計画の申請手続のスケジュール(今後変更の可能性有)
現状公開されている事業適応計画の申請手続のスケジュールは以下の通りです。
①事前相談<1〜2ヶ月>
②-A計画申請(審査スタート)<1ヶ月程度>
所定の申請書+添付書類を提出する
②-B課税の特例への適合確認申請(計画審査と並行)
適合すると判断された場合は、認定書又は確認書が発行される
繰越欠損金の控除上限の特例又はDX投資促進税制の適用を受ける場合、
課税の特例(要件)への適合性の確認は、計画の審査プロセスと併せて行われます。
課税の特例(要件)への適合性が確認された場合は、その旨が認定書又は確認書において表示されます。
③計画の認定(計画開始)<原則5年以内>
④税制対象投資(設備取得など)を実施し、事業に活用
⑤税務申告までに証明書発行(繰越欠損金の控除上限の特例を受ける場合)
4-2 事業適応計画関連の税制措置の適用を受けるための手続フロー(今後変更の可能性有)
現状公開されている事業適応計画関連の税制措置の適用を受けるための手続フローは以下の通りです。
①事業適応計画の認定・公表(認定されると原則公表)
※「課税の特例」基準への適合確認は計画の申請と同時に実施
適合すると判断された場合は、認定書又は確認書が発行される
②税制対象となる投資(設備取得など)を実施し、活用
*成長発展事業適応(繰越欠損金の控除上限の特例)の場合
③投資実績額の証明書発行
④税務申告+③で発行した証明書の写しを提出
*情報技術事業適応(DX投資促進税制)の場合
③なし
④税務申告+認定計画の写し、①で発行された認定書又は確認書の写しを提出
⑤事業適応計画の「実施状況報告書」を毎年提出・公表
※報告書の提出時期は原則、認定事業者の事業年度終了後3ヶ月以内
5. まとめ
産業競争力強化法自体は、あまりにもその内容の幅が広く、全てについて理解するのは専門家でなければ難しいものです。
今回はこの法律の中で、中小企業のDX推進に関連する部分にポイントを絞ってお伝えしましたが、
一部分だけであるとしてもご理解いただけたでしょうか。
今回の改正については、国としてもDX推進に力を入れていることが感じられる内容であったと思います。
DX推進にあたって、特にDX税制はメリットが大きいものです。活用のためには事業適応計画の認定が必要となりますので、
活用を検討されている企業はできるだけ早く動き出すことをお勧めいたします。
おすすめ資料ランキング





【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-





















