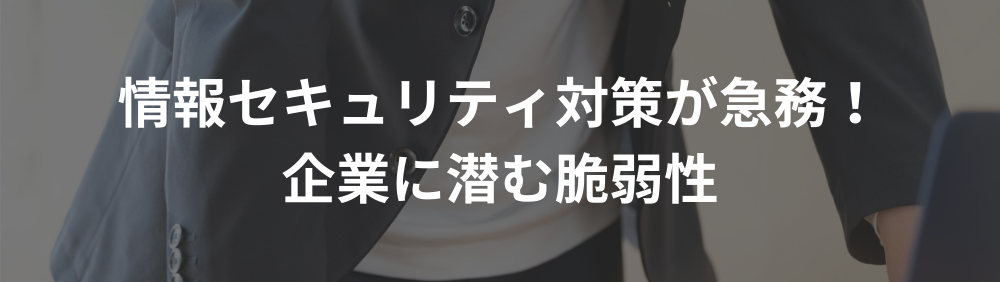
目立った問題が起きていない場合、社内ネットワークのセキュリティ対策は十分だと思ってしまいがちです。
しかし、実際には数多くの「脆弱性」が潜んでいるケースがあります。
情報セキュリティ対策を行うためには、脆弱性への理解が必須です。
こちらの記事では、脆弱性の概念や脆弱性をカバーするための対策についてお話しします。
情報セキュリティで知っておきたい脆弱性・脅威・リスクの概念
情報セキュリティの話題でしばしば登場するのが「脆弱性」「脅威」「リスク」といったキーワードです。
まずはこうしたワードの意味についておさらいしていきましょう。
脆弱性
「脆弱性」とは、つまり「脆くて弱い性質」を意味します。
外部からの攻撃や負荷に弱く、簡単に損壊してしまうということです。
情報セキュリティにおいては、ソフトウェア・システムに存在している欠陥や不具合を意味します。
「脆弱性がある」「脆弱性を抱えている」といった使い方が一般的です。
当然ながら、脆弱性はソフトウェア・システムにとって好ましい性質ではありません。
しかし、脆弱性がまったくない完璧なシステムは存在しないことも事実です。
多くのサイバー攻撃は、この脆弱性を狙ってシステムに損害を与えます。
システム開発の現場では、アップデートプログラムを開発・提供することによってサイバー攻撃を退けています。
しかし、違う脆弱性を突く新しいサイバー攻撃が登場してくるため、この競争は事実上終わることがありません。
脅威
一般的に「脅威」は危険や損害をもたらすもの、その事象の発生元として使われます。
情報セキュリティにおいては、データに危険・被害を加える存在という意味です。
サイバー攻撃そのものや、ネットワークに侵入してくるマルウェアなどを指して使われます。
上述した定義にもとづくと、企業が警戒しなければならないのは外部からの脅威だけではありません。
内部で発生する脅威も存在します。
社員による情報の持ち出しや人為的なミスによる情報流出も、脅威の一種として考えなければなりません。
リスク
リスクとは危険性のことで、情報セキュリティにおいてはサイバー攻撃によって被害を受ける可能性を意味します。
セキュリティ対策では、脆弱性・脅威・リスクを可能な限りなくすことが重要な課題です。
リスクを大きさで判断する考え方もあります。
リスクの大きさを判定するためには、保護している情報資産の価値を把握しなければなりません。
リスクの大きさは以下のような計算式で割り出すことができます。
リスクの大きさ=情報資産の価値×脅威の大きさ×脆弱性のレベル
脆弱性の原因とは
上述したとおり、システムの脆弱性を完全になくすことは困難です。
多くのシステム・ソフトウェアは、脆弱性を残したまま使用されています。
なぜ脆弱性は発生してしまうのでしょうか。
以下では脆弱性の代表的な原因について解説します。
設計の段階で想定されていない問題
システムは開発元とユーザーの間で合意された要件に沿って開発されます。
しかし、実際にリリースしたシステムは当初想定されていた利用方法で運用されるとは限りません。
開発時にテストしていない部分には、脆弱性が残されているケースがあります。
システムの利用方法が多様化している現在、すべての利用方法をカバーしてテストを行うことは事実上不可能です。
設計のミス
開発元はプロフェッショナルですが、リリースされたシステムには設計ミスが残されているケースも少なくありません。
設計ミスの内容によっては、そのまま脆弱性となることもあります。
アップデートの遅れ
上述した理由からシステムがリリースされた段階ではまだ多数の脆弱性が残されています。
開発元は脆弱性に気付き次第アップデートプログラムを開発し配布しますが、サイバー攻撃の進化に追いつけるかは開発元次第です。
また、そもそもユーザー側でアップデートプログラムを適応しなければ、脆弱性は残されたままになってしまいます。
脆弱性を狙うサイバー攻撃の手口
脆弱性を狙うサイバー攻撃の例として以下のようなものが挙げられます。
マルウェア
コンピュータウイルスをはじめとしたマルウェアは、代表的なサイバー攻撃であり、脅威です。
マルウェアに感染するとコンピュータにはさまざまな悪影響が起こります。
これまで脆弱性を狙うさまざまなマルウェアが開発されており、今後も開発が止まることは考えられません。
ゼロデイ攻撃
ゼロデイ攻撃とは、まだ明るみに出ていない脆弱性を突いたサイバー攻撃の総称です。
開発元はまだ把握すらしていないため、当然ながら対応するアップデートプログラムは開発されていません。
バックドア
バックドアは「後ろのドア」、つまり「裏口」を意味します。
システム開発においては、検証のための設けられる外部への通信経路を指します。
システムのリリース時も放置されることが多く、そのまま脆弱性に変化するケースがあります。
脆弱性によって生じ得るリスク
さまざまなリスクを回避するためにも、脆弱性を是正しなければなりません。
生じ得るリスクの例をご紹介します。
情報漏えい
脆弱性によって情報漏えいが起こり得ます。
企業をネットワークに侵入するマルウェアの多くは、内部の情報を盗み取るように設計されています。
企業で保有するデータは、個人情報や新しい企画など、外部への流出が許されない性質のものが大半です。
企業で情報漏えいが起きると情報の流出によって甚大な被害を受けるほか、管理体制に関する責任を追及されます。
乗っ取り
端末やシステムを乗っ取られてしまうこともあります。
外部の悪意あるユーザーによりシステムが乗っ取られると、データの書き換えや外部への情報送信など、外部ユーザーの思いのままの操作を行われてしまうでしょう。
システムを犯罪に利用されてしまうケースもあります。
不正アクセス
ネットバンク、Webサイト、SNSなど企業で利用しているサービスのアカウントに不正アクセスされてしまうことも考えられます
ネットバンクにログインされれば、資金を不正に送金されてしまうかもしれません。
WebサイトやSNSへの不正アクセスにより、企業側で意図していない情報が発信されてしまうケースもあります。
脆弱性をカバーするための情報セキュリティ対策
システム内の脆弱性は常に存在しているという前提で対策を講じていくことが大切です。
以下では、脆弱性をカバーするための具体的なセキュリティ対策をご紹介します。
セキュリティソフトウェアのアップデート
OSやセキュリティソフトウェアの開発元は脆弱性をカバーするためのアップデートプログラムを積極的に配布しています。
利用しているOSやセキュリティソフトウェアが最新のバージョンになっているか、常に確認しましょう。
また、アップデートプログラムの配布が通知された場合は、すぐに適用させるように心がけてください。
最新の脆弱性情報へのキャッチアップ
最新の脆弱性情報にキャッチアップすることも大切です。
発覚した脆弱性に関する情報は、開発元のホームページや専門のニュースサイトで発表されます。
常にこうした情報ソースから情報を収集し、利用しているシステムに未知の脆弱性がないか確認するように努めてください。
なお、脆弱性情報を調べる際は、一次情報のソースを確認することが非常に重要です。
一次情報とは、企業や組織が直接的に行った考察・調査から得られた結果であり、オリジナルの情報のことです。
開発元が発表した情報や、ニュースサイトの情報は一次情報として分類できます。
一次情報は伝えられた人の曲解や誤解が含まれておらず、情報として正確です。
対して、他の人を介して伝えられる二次情報は正確性が低下します。
脆弱性情報は正確性が重要なため、一次情報をソースとするように意識してください。
セキュリティ診断サービスの利用
アップデートや情報のキャッチアップだけで安心できない場合は、セキュリティ診断サービスを利用することをおすすめします。
セキュリティ診断サービスとは、システムやソフトウェアの顕在化していない脆弱性を検知するサービスのことです。
現在はWebアプリケーションやWebサイトなど、さまざまなシステムを対象としたセキュリティ診断サービスが提供されています。
無料のセキュリティ診断サービスもありますが、悪質なものもあるため利用に際しては注意が必要です。
万全を期す場合は、有料、かつ多くのユーザーに信頼されているセキュリティ診断サービスを利用しましょう。
UTMの導入
UTMとは、複数のセキュリティ機能を集約したハードウェアを設置し企業ネットワークを守る取り組み、もしくはそのためのハードウェアそのものを指します。
日本語では「総合脅威管理」と訳され、無数の脅威から効率的にネットワークを守る取り組みとして普及しています。
UTMに搭載されている「IPS」というシステムは、脆弱性をカバーするために開発されています。
専用機器を設置しておけば、企業で使用しているシステム・ソフトウェアの脆弱性を自動的にカバーし、脅威の侵入を防ぐことが可能です。
まとめ
今回ご紹介したように、リリース後のシステムであってもさまざまな脆弱性が存在しています。
開発側は脆弱性を根絶するように努力していますが、サイバー攻撃から自社の情報を守るためにはユーザー側の努力や意識も必要です。
スターティアでは、システムの脆弱性をカバーし、社内ネットワークのセキュリティを強化できるUTMを提供しています。
セキュリティソフトウェアだけでは防ぎきれないマルウェアの侵入を検知し、被害を回避できるセキュリティ機器です。
システムの脆弱性を懸念している企業様は、お気軽にご相談ください。
おすすめ資料ランキング





【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-





















