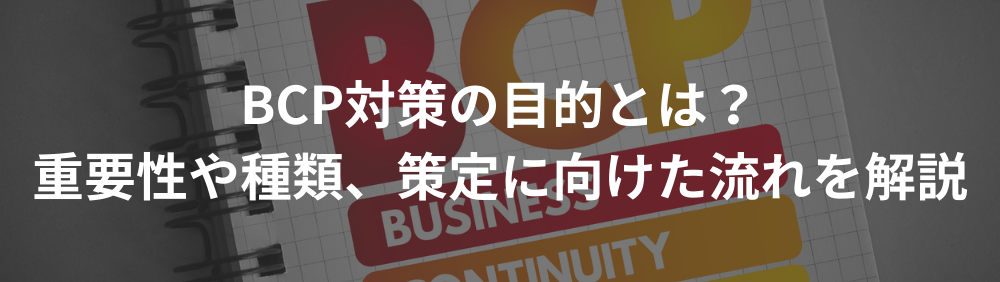
地震、台風、豪雨、豪雪など、日本では毎年のように災害が起きています。
企業の施設がこうした災害の被害を受け、事業継続が困難になるケースも少なくありません。
こうした状況のなか、重要性が高まってきているのが「BCP対策」です。
この記事では、BCP対策の概要や策定方法について解説します。
BCP対策とは
BCPとは、「Business Continuity Plan」の略です。
日本語では、「ビジネスを継続していくための計画」と訳されます。
BPC対策は近年、頻発している自然災害、火災、テロ行為などを想定しています。
こうした事態が事業にもたらす影響を最小限にとどめるための取り組みです。
一般的に行われている防災対策とBCP対策は大きく異なります。
BCP対策は、企業に起こり得る非常事態すべてに対して備えているのに対し、防災対策が想定しているのは自然災害のみです。
その点では、BCP対策のほうがさまざまな事態をカバーするための取り組みと言えます。
例として、直近では新型コロナウイルス関連のBCP対策を行う企業も少なくありません。
「社内でクラスターが発生した場合に業務への影響を最小限にするためにはどうすべきか?」といった検討もBCP対策の範疇です。
BCP対策の目的
BCP対策には具体的にどういった目的があるのでしょうか。
効果的なBCP対策を行うためにも、目的を明確にしておくことが大切です。
代表的なBCP対策の目的について解説します。
緊急事態がもたらす事業への影響を小さくすること
代表的な目的は、緊急事態による事業への影響を最小限にすることです。
緊急事態が起きた際、とるべき対策が定まっていなければ、業務に著しい停滞が生じてしまいます。
普段どおりの業務が困難な場合も、混乱を防ぎ可能な限り業務への影響を少なくすることが大切です。
緊急事態にもできる代替業務を決めておけば、通常業務ができない時間を無駄にせずにすみます。
迅速に通常業務へ復旧すること
緊急事態に対して事前の対策を十分に用意していたとしても、少なからず業務への影響はあります。
通常業務へ普及するまでのタイムロスが長ければ、機会損失が生まれてしまうかもしれません。
顧客の流出により、復旧後の売り上げ回復が難しくなることも考えられます。
速やかに復旧できるよう、対処の流れや役割分担を決めておくことも重要なBCP対策です。
従業員の様子を確認すること
従業員を守ることも、BCP対策の重要な目的です。
業務中に企業の管理下で緊急事態が起きた場合は、従業員の安全を最優先にした行動ができるよう、マニュアル等を整備しておく必要があります。
ただし、万が一従業員が負傷・死亡した際に、会社側で直ちに講じることができる策はありません。
連絡手段がない場合、出勤の必要がない限りは通信が回復してから安否確認を行えば問題ないと考えられています。
また、無理に勤務・出社させることは、従業員の生命を脅かすことになるため好ましくありません。
BCP対策が重要な理由
以前は、発生した緊急事態に対して個別に対策を行うのが一般的でした。
しかし、近年では対策しなければならない緊急事態の多さから、個別対応だけでは限界があると考えられています。
日本では、この10年余りで大型地震、豪雨、台風など、ビジネスの継続を脅かすような事態は毎年のように起きています。
また、企業にとってのリスクはこのような自然災害だけとは限りません。サイバー攻撃、テロなど、多くの危険が存在しています。
近年では、新型コロナウイルスも企業が直面しなければならないリスクのひとつです。
数多くのリスクに備え、それまでの個別対応に代替する考えとして台頭してきたのがBCP対策です。
緊急事態に対して個別に対応することを目指すのではなく、「事業を継続するためにすべきことを定める」という包括的な対応を行うのがBCP対策の本質です。
とりわけ日本では災害の多さが目立つ日本では、BCP対策についてしっかりと考えておくことは重要と言えるでしょう。
3種類のBCP対策
続いて、具体的なBCP対策について考えていきましょう。
BCP対策は「自然災害への対策」「外的な問題への対策」「内的な問題への対策」に分けられます。
以下では、それぞれの種類について解説しましょう。
自然災害に対するBCP対策
地震、台風、大雪、豪雨などへの対策です。予測するのが難しいため、あらかじめ発生時の行動について策定しておく必要があります。
また、事業の継続や再開以上に、従業員の安全を確保するためのフローを決めておくことが大切です。
具体的には、以下のような内容を明確にしておくことが求められます。
- 避難の経路や方法
- 安否確認のルールや方法
- 非常時の連絡先リスト
- 業務の復旧フロー
- 復旧時のデータ管理方法
外的な問題に対するBCP対策
取引先やサプライチェーン上にある企業の倒産、テロやサイバー攻撃など、さまざまな外的問題が考えられます。
セキュリティや監査の強化でリスク自体をなくすことが理想ですが、万が一発生してしまった時のことも考えておかなければなりません。
以下のような項目について、具体的に決めておく必要があります。
- 体外的な通知の手順と担当者
- 代わりの仕入れ先(仕入れ先が利用できなくなった場合)
- 代わりに利用するシステム(導入システムが利用できなくなった場合)
- データの復旧手順
- 復旧したデータの取り扱い
内的な問題に対するBCP対策
過失、または故意の情報漏えい、不祥事など、内部の人間による問題も起こり得ます。
近年は、アルバイト職員が大きな問題を起こすケースも少なくありません。
こうした問題によって事業が完全に止まることは多くありませんが、対外的な信用を大きく損ねてしまうことは避けられません。
以下のような対応をあらかじめ決めておくことで、被害を最小限にとどめることが可能です。
- 謝罪の手順や文言
- 起こり得るシナリオを想定した対応フロー
- 問題発生時の連絡リスト
- 問題再発防止のための見直しフロー
BCP対策の策定ポイント
以下では、さまざまな事態へ対応できるBCP対策を策定するためのポイントについて解説します。
従業員への指示・対応を明確にしておく
施設や機器が無事だったとしても、従業員がいなければ業務を再開できません。
従業員に対してどのように業務に戻ればいいのか、少人数で業務を継続する方法など、指示や対応を明確にしておく必要があります。
設備の損壊を想定しておく
近年の大型災害では、企業の施設そのものや設備が損壊することも少なくありません。
自社サーバーが損壊すれば、システムの利用やデータの引き出しが困難になるでしょう。
工場が損壊し、生産を止めなければならないこともあります。
こうした損壊をあらかじめ想定し、代替手段を用意していくことが大切です。
有事の際に利用できる資金調達方法を用意しておく
緊急事態の事業停止によってどの程度の経済的損害が出るのかコストシミュレーションしておきましょう。
その損害をカバーできる資金調達方法を用意しておくと、資金面でも安心できます。
保険の契約や公的融資制度の利用も検討してください。
リーダーシップをとる人や代行できる人を明確にしておく
緊急事態において指揮する人がいなければ、現場が混乱してしまいます。
リーダーシップをとる人を明確にしておきましょう。
その人が不在のケースも考えられるため、代行できる人を複数人リストアップしておく必要があります。
データのバックアップを取っておく
施設が損害を受けると、自社サーバーに格納しているデータが損失してしまうことがあります。
重要なデータが損失してしまった場合、すぐに事業を復旧することは難しいでしょう。
遠隔地のサーバーやクラウドのサーバーなどにデータをバックアップしておくことで、リスクを分散できます。
BCP対策を策定する流れ
BCP対策を策定する一般的な流れを解説します。
専任チームの編成
BCP対策を牽引する専任チームを編成します。
さまざまな角度からの意見が求められるため、各部門から代表者を募るのが一般的です。
取りまとめを行う部を決めておくと策定がスムーズに進みます。
優先的に保護する事業の検討
すべての事業に対し平等に対策を行うのは困難です。
そのため、企業の存続に与える影響度から事業の優先度を決め、優先度が高い事業から対策していくことになります。
その事業が停止したことによってどの程度の損害があるのか、その事業はどの程度の頻度で行われるのか、といった基準から優先度を判断します。
可能性のある被害の想定
事業が受ける可能性がある被害について想定します。
上記の「自然災害」「外的な問題」「内的な問題」から、具体的に起こり得る被害について深掘りしていきましょう。
起こり得る緊急事態の種類を検討したうえで、可能であればそれぞれの緊急事態の発生率についても調査しましょう。
実際に被害を受けた場合に復旧にはどの程度のコストと期間がかかるか、また復旧期間でどの程度の損失が発生するか、といった内容についてもシミュレーションしてください。
事業復旧に向けた動き方の検討
最後に、事業復旧に向けた具体的な動きについて検討します。
従業員への指示、設備損壊への対応、リーダーシップの所在の明確化など、上記のポイントを意識しましょう。
必要に応じて対応の訓練を行うことも大切です。
また、策定したBCP対策は定期的に見直し、アップデートしていくことが求められます。
まとめ
日本では大型災害が多発しています。
そのため、すべての国内企業にとってBCP対策は他人事ではありません。
いつ、どんなことが起こるかは予想できませんが、可能な限りで多様なケースを想定し、緊急事態から速やかに復旧できる体制を整えましょう。
近年の大型災害では、火災などで企業の紙資料が消失したケースも少なくありません。
紙で保管している書類をデータに起こしてバックアップをとることもBCP対策につながります。
複合機を導入すれば、紙資料のデータ化が可能です。
スターティアでは、コピー機・複合機の導入サポートを実施しています。
データのバックアップにご利用いただけるクラウド構築・保守のサービスもおすすめです。
BCP対策を実施したいとお考えの企業様は、お気軽にご相談ください。
おすすめ資料ランキング





【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-





















