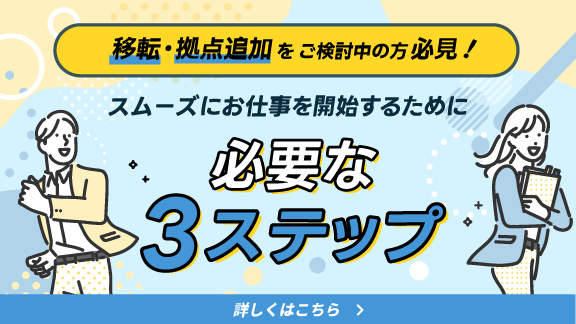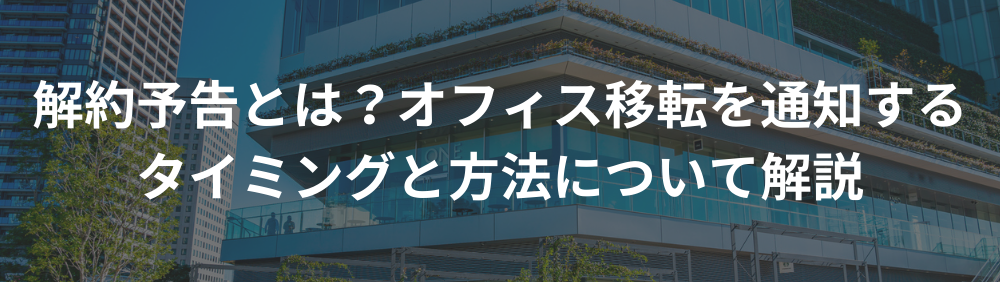
オフィス移転をするためには、現オフィスの解約予約を行わなければなりません。
この記事では、解約予告の概要やタイミング、具体的な方法やポイントについて解説します。
解約予告とは
解約予告とは、賃貸借契約の満了前に解約するために必要な手続きです。
オーナーや管理会社などに対し、何らかの理由から解約の意向があることを報告することを意味します。
マンションなどの住宅のほか、オフィスの解約でも一般的な手続きです。
オフィスの賃貸借契約では、一般的に2~3年間の契約期間が定められています。
通常、この契約期間満了時に更新・退去のどちらかをすることになります。満了前に退去したい場合は、解約予告の手続きが必要です。
オフィスの場合、事業展開や作業環境改善の必要性から、契約満了前に退去するケースが少なくありません。
そのため賃貸借契約の満了前に正しく解約する方法について理解しておく必要があります。
解約予告が必要な理由
なぜ、賃貸借契約では解約予告が求められているのでしょうか。
解約予告の必要性について理解しておきましょう。
解約予告が必要とされる理由は、主にオーナーの都合です。
オーナーは、借主から賃貸料を得ています。賃貸料を継続して獲得するためには、常に借主の存在が必要です。
しかし、借主が予告なく解約してしまった場合、次の借主をすぐに見つけることは難しいでしょう。
そのため、オーナーの家賃収入が突然途絶えてしまうことになります。
オフィスのように賃貸料が高い物件の場合は特に、次に借主を見つけるのは容易ではありません。
一方、解約が前もって予告されていれば、次の借主を余裕を持って探すことができます。
つまり、解約予告は主にオーナーのリスク軽減のための定められている仕組みです。
解約予告のルールについては通常、契約書にも記載されています。
契約の内容によっては、解約予告のルールを破って解約した場合に違約金を請求されるケースがあります。
解約予告を行うタイミング
解約・退去を決めた場合、いつ解約予告を行うべきなのでしょうか。以下では、解約予告を行うタイミングについて解説します。
解約予告期間とは
解約予告期間とは、現在住んでいる部屋を解約する前に、解約の意思を伝えなければならない期限のことです。
オーナーにとっては、次の入居者探しに費やせる期間となります。
契約の内容によっては細かな際は差異がありますが、一般的な解約予告期間は6カ月です。
【例】5月にオフィスを移転するためには
上記のとおり、一般的な解約予告期間は6カ月です。
この点も踏まえ、例として5月にオフィスを移転するための大まかなスケジュールをイメージしてみましょう。
退去の6カ月前に解約予告を行わなければならないため、5月中にオフィスを移転するためには11月末までの解約予告がマストです。
その他に、新しいオフィスの物件探しなどを行います。
新オフィスを業務環境として整備しなければならないため、4月には新しい物件の契約を開始して工事を始めるのが一般的です。
5月はじめに移転を済ませておけば、余裕を持って旧オフィスの原状回復工事を行えます。
その後、予定していた解約日を迎え、旧オフィスでの契約は終了となります。
5月は春に採用した新入社員の研修が落ち着くことから、多くの企業がオフィスを移転する時期です。
5月のオフィス移転を検討している場合は、解約予告をはじめとした意思決定のタイムリミットが11月中であることをあらかじめ知っておきましょう。
解約予告の方法
解約予告の方法は賃貸借契約のなかで定められています。
オフィスを移転する場合は、まず契約の内容を確認し、記載されている方法に準拠して解約予告を行ってください。
一般的には、書類の記入・提出によって解約予告を行います。
不動産会社側で書類を用意している場合があるため、問い合わせてみましょう。
提出する解約通知書には、以下のような内容を記載します。
- 解約通知する日付
- オーナーの名称
- 借主の名称
- 物件の名称
- 物件の所在地
- 解約の意志
- 通知後の支払いに関する内容
- 敷金や保証金に関する内容
書面での解約予告が必要かどうかは、契約内容によって異なります。
ただし、解約の意志を明確な形で残しておかなかったことが原因で、オーナーと借主の間でトラブルが起こることは少なくありません。
そのため、契約内容に関わらず解約予告を書類で残しておくと安心でしょう。
オフィスの解約予告を行う際に確認するポイント
オフィスの移転には、解約予告をはじめ煩雑な手続きが伴います。
ぎりぎりになってスケジュールに余裕がなくなり、慌ただしい移転になってしまうことも少なくありません。
最悪の場合、新オフィスの準備が完了しないまま業務を開始しなければならないことも考えられます。
スムーズにオフィス移転を進めるため、オフィスの解約予告を行う際には、以下のようなポイントを確認しておきましょう。
オフィス移転の目的を明確に定める
まずは、オフィス移転の目的を明確に定めること大切です。
目的をはっきりさせることで、次のオフィスに求める条件が定まってきます。
解約予告に関しても、オフィス移転の目的が定まってから行うのがおすすめです。
目的があいまいなまま解約予告を出すと、物件探しに時間がかかり、結果的に契約終了タイミングの近辺が慌ただしくなってしまうかもしれません。
現オフィスの契約書を確認する
解約予告の方法については契約書に記載されています。
また、契約期間や解約時の違約金の有無なども契約によって異なるため、契約書を詳細に確認してください。
契約内容に関してわからない点があれば、不動産会社に問い合わせましょう。
移転スケジュールを決める
オフィスの移転には、レイアウトの検討、什器・家具の購入、新オフィスの工事、各種届出などさまざまな業務が発生します。
場当たり的に進めると抜け落ちが発生しやすいため、移転スケジュールを決めて行動しましょう。
また、家賃の二重払いを可能な限り少なくするためにも、おおよその移転時期について決めておくことをおすすめします。
解約予告で知っておくべきポイント
解約予告について知っておいていただきたいポイントを紹介します。
解約予告期間は交渉可能
解約予告は基本的にオーナーの都合で設けられている仕組みです。
解約予告期間は長ければ長いほど、オーナーは次の入居者探しを余裕を持って行えます。
対して、借主にとっては、解約予告が長いほど不都合が生じてくるのです。
例として、移転先の物件が決まってから解約予告を出すケースを想定してみましょう。
解約予告期間が長いと、新オフィスの契約が始まってからもしばらくは旧オフィスの解約を行えず、家賃を二重で支払う期間が長くなってしまいます。
このことから、特に新オフィスを決めてから解約予告を行う場合は、解約予告期間が短いほど好都合です。
解約予告期間を短くしたい場合は、オーナーに交渉してみるのもひとつの方法です。
オーナーによっては解約予告期間の短縮に応じてくれるケースがあります。
二重払いの期間を短くしたい場合は、積極的に交渉してください。
ただし、ビルの入居者に対し一様の契約内容が提示されている場合は、1人に契約者に特別な対応をすることが難しい場合があります。
トラブルになってしまう可能性もあるため、解約予告期間の短縮に関してオーナーが難色を示す場合は、無理やり交渉を続けることは控えてください。
解約予告は取り消せる可能性がある
解約予告を行った後に、オフィス移転自体を見直すことになったり、条件に合う物件が見つからなかったりすることも考えられます。
基本的に解約予告の取り消しはできませんが、こうした事情がある場合は一度オーナーに相談してみるのもひとつの方法です。
上記のとおり、解約予告期間は次のオーナーにとって空室期間をなくすための仕組みです。
次の入居者が決まっていない状態で現契約が終了し、空室期間が生まれることはオーナーにとって好ましくありません。
そのため、次の入居者が決まっていなければ解約予告の取り消しを受け付けてくれる可能性があります。
オフィス移転に発生する費用の内訳
オフィス移転の予算を決める際には、発生する費用の内訳について知っておくことが大切です。
オフィス移転でかかる費用の代表的な内訳について解説します。
敷金
新しいオフィスに入居する際には、敷金を支払う必要があります。
オフィス契約の敷金は一般住宅の敷金よりも高額であり、賃料の6~12カ月分が相場です。
退去時には、支払った敷金から原状回復費を差し引いた金額が返還されます。
ただし、オフィスの敷金には償却の概念があり、支払った敷金のうち一定割合は償却費として返還されない仕組みになっています。
償却の割合については、契約書に記載されているため確認しましょう。
原状回復費
原状回復費は、オフィスを入居時の状態に戻すための原状回復工事を行うための費用です。
一般住宅とは異なり、オフィスの原状回復費は破損や劣化の内容に関わらず、基本的に借主が100%負担します。
原状回復費は1坪あたり40,000円程度が相場です。
ただし、依頼する業者やオフィスの使用状況によって費用は増減します。
入居工事費
新しく契約したオフィスでそのまま業務を開始することはできません。
通常は想定している環境を構築するための入居工事を行う必要があります。
入居工事費の相場は1坪あたり40,000円程度です。
ただし、特殊なレイアウトやデザインを要求する場合は、さらに費用がかかることがあります。
引越し費用
引越し費用も予算に組み込んでおく必要があります。
オフィス移転の場合、引越し作業費の目安は社員1人あたり50,000円程度だと考えられています。
まとめ
オフィス移転を検討している場合は、遅くても移転を希望している日の6カ月前には解約予告を行いましょう。
正確な解約予告期間については契約書に記載されているため、あらかじめ確認してください。
スターティアでは、煩雑なオフィス移転の作業をサポートするオフィス移転・デザイン、オフィス移転コンシェルジュのサービスを提供しています。
オフィス移転を予定している場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
おすすめ資料ランキング





【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-