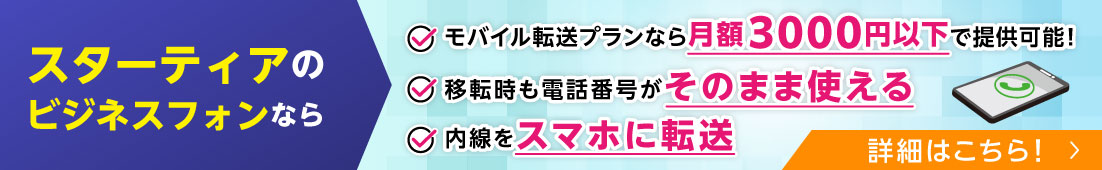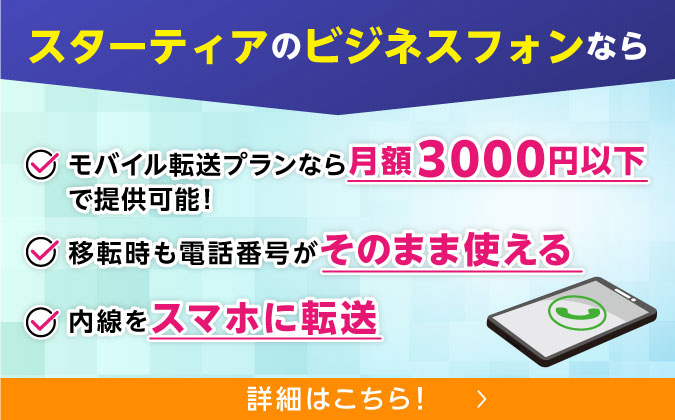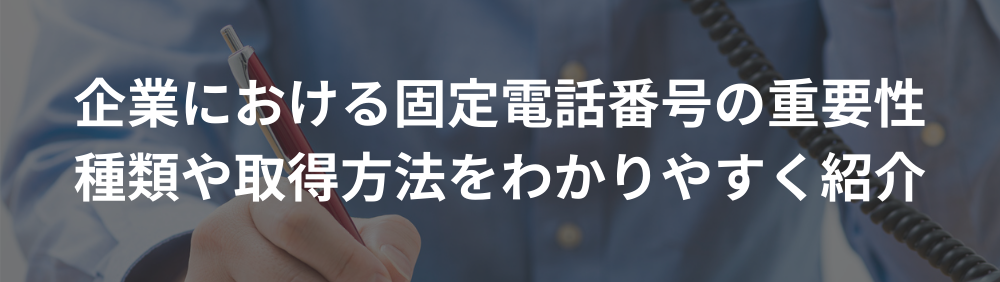
ビジネスシーンでは、IP電話より固定電話の番号が信用されやすいといわれます。
とはいえ、なぜ固定電話番号が重要視されるのか、よくわからないとの声も少なくないでしょう。
そこで今回は、固定電話番号の概要を解説し、ビジネスの場で固定電話番号を取得したほうがよい理由をご紹介します。
固定電話番号とは?
固定電話番号とは、通話の相手を識別するために使われる番号のひとつです。
日本の場合、0から9までの数字を10桁で組み合わせています。
具体的には、「0-市外局番-市内局番-加入者番号」の形式で構成されています。
携帯電話番号との違い
固定電話番号と携帯電話番号の主な違いは、番号の先頭部分の差です。
まず、固定電話番号は、一般的に「0-市外局番」から始まります。
最初の「0」は、国内プレフィックスと呼ばれる番号です。
電話をかけるとき、国内通話であることを示す合図の役割を果たします。
また、固定電話番号の先頭部分は、国内プレフィックスと市外局番が組み合わされています。
一方、携帯電話番号の先頭は、基本的に「090」「080」「070」の3つです。
固定電話と携帯電話の番号は先頭部分が異なり、これによって両者を区別できるようになっています。
市内局番と市外局番の違い
市外局番は、都道府県など国内の広い地域を区別する目的で設定された番号です。
通常、日本列島の北側から順に、小さい数字が用いられています。
いくつか例を挙げると、北海道は「1」、東京都23区は「3」、大阪は「6」、九州・沖縄は「9」です。
慣例的には、国内プレフィックスを含めた「01」や「03」が、市外局番として認識されています。
現在、市外局番は1~4桁であり、2桁は横浜「45」や京都「75」、3桁は栃木「282」や宮崎「985」、4桁は伊豆大島「4992」などが知られています。
市内局番は、主に市区町村単位で、1~4桁の番号が割り振られる仕組みです。
また、市外局番とは、合計5桁になる構成で組み合わされます。
市外局番が1桁なら市内局番は4桁、同じく前者が4桁であれば後者は1桁になり、いずれも合計5桁になる形式です。
一般的な固定電話の番号は、市外局番で都道府県などが選別され、市内局番で市区町村といった特定の地域が絞り込まれるように設定されています。
固定電話番号の種類
固定電話番号の種類は、大きくわけると「00」から始まるタイプをはじめ5種類です。
他に、市内通話で固定電話へ発信するとき使われる、「2~9」で始まる番号もあります。
引用:電話番号に関するQ&A/総務省
00から始まる番号
「00」から始まる番号は、電話会社を選択するとき用いられる電話番号です。
通常、NTT東日本・西日本経由で電話をかける場合、10桁の電話番号を使えば通話したい相手に発信できます。
それに対し、発信時に中継する電話会社を指定する際は、「00」が必要です。
国内の電話会社は、「00」から始まる事業者識別番号を所持しています。
電話会社がA社の場合、「00xxa」といった具合です。
この事業者識別番号を電話番号の先頭につけると、NTT東日本・西日本以外の電話会社を指定できます。
その後に10桁の番号を続けてダイヤルすれば、指定した電話会社を経由し、相手に電話をかけられます。
0A0から始まる番号
「0A0」から始まる番号は、携帯電話やPHSに割り当てられる種類です。
携帯電話・PHSの場合、最初の3桁に「090」「080」「070」の3通りが使われています。
もともと携帯電話の番号は「090」であり、PHSの「070」と区別されていました。
2014年10月以降は、携帯電話とPHSの間で番号の移動が可能になり、区別する必要がなくなっています。
携帯電話・PHSの番号を移動できる仕組みは、番号ポータビリティと呼ばれる制度によるものです。
この制度により、それぞれの利用者は、携帯会社を変更したとき同じ番号を継続利用できるようになりました。
また、発信者課金ポケットベルには同じ「0A0」のうち「020」、IP電話は「050」が用いられています。
0AB0から始まる番号
「0AB0」から始まる番号は、法人向けの電話サービスなどで提供される形式です。
電話会社は、電話の利用者に特殊なサービスを提供するとき、この形式を国内共通の番号として使用しています。
代表的な例は、フリーダイヤルの「0120」や「0800」です。
通常、電話の通話料は発信者側で負担しますが、フリーダイヤルを利用すると、受信者側が支払うことになります。
この場合、発信者による負担は不要であり、無料で電話をかけられます。
また、「0570」は、NTTが提供しているナビダイヤルの番号です。
さらにNTT提供の情報料回収代行「0990」や呼数集計(テレドーム)「0180」も特殊な部類に入ります。
0ABCから始まる番号
「0ABC」から始まる番号は、市外通話で固定電話に発信するとき使われる種類です。
実のところ、この形式は、国内プレフィックスの「0」と市外局番が組み合わさった番号を意味しています。
たとえば、「0A」は北海道「01」、「0AB」は神戸「078」、「0ABC」は鳥取「0857」に該当します。
固定電話に向けた市外通話は、フリーダイヤルや緊急通報など特殊なケースを除き、基本的に市外局番が不可欠なのです。
なお、市外局番は必ずしも「0ABC」とは限らず、御殿場市「0550」のように「0AB0」に相当する番号もあります。
1から始まる番号
「1」から始まる番号は、主に緊急性や公共性を要する用途で使われる電話番号です。
この形式は、「1xx」の3桁のみで表現されるケースが多く見られます。
都道府県や市区町村を示す局番はなく、桁数の少ないシンプルな構造が特徴です。
電話番号が短く、覚えやすいうえ簡単にダイヤルできるため、緊急通報や公共的なサービスに割り振られます。
代表例なのは、電話番号の案内「104」・警察への通報「110」・電報の受付「115」・時報「117」・消防庁への通報「119」や天気予報「177」などです。
また、海上保安機関への通報は「118」、災害用伝言ダイヤルは「171」となります。
いずれも重要性の高い用途であり、各用途で使われる番号は、電話会社に関係なく統一されています。
2~9から始まる番号
「2~9」から始まる番号は、市内通話で固定電話に連絡するとき使用する部分です。
この部分は、固定電話番号のうち、市内局番に該当します。
市内通話の場合、電話の発信者は、同じ市区町村などにある固定電話へ連絡を入れます。
発信元と受信側の市区町村が同じなら、固定電話の市外局番は同一の番号であり、一般的に都道府県から絞り込む必要はありません。
そのため、このケースは市外局番が不要であり、「2~9」から始まる市内局番と加入者番号だけダイヤルすれば電話がつながります。
050電話番号とは?
050電話番号は、「0A0」のうちIP電話に割り当てられる電話番号の種類です。
一般的な固定電話の番号と異なり、11桁で構成されています。
IP電話とは?
IP電話は、インターネットの回線を介して音声通話できるシステムです。
一般的な固定電話はアナログ回線を使用し、基地局を経由して通話する仕組みとなっています。
それぞれの電話機は、電話線で物理的につながっている状態で、いずれも基地局を中継します。
一方のIP電話は、アナログ音声をデジタル化し、インターネットを介して送受信する方式を採用しています。
デジタルデータはネット経由で送られた後、アナログ音声に再構築されるため、音声による通話が可能になっています。
その上で、通話相手との距離によって利用料金が変わらないため、固定電話よりも通話料金を抑えられる特徴があります。
IP電話の種類と特徴
IP電話の種類は、大きくわけて「電話番号なし」と「電話番号あり」の2つがあります。
一部のサービスは、IDを識別する方法により、相互通話が可能になっています。
「電話番号なし」の場合、特定の電話番号を取得せずに通話できるのが特徴です。
「電話番号あり」は、「0AB-J型」と「050型」の2種類に大別されます。
そのうち「0AB-J型」は、通常の固定電話と同じく、「0」で始まる10桁の電話番号が割り当てられます。
この構成により、電話番号の先頭は、都道府県などと結びついた市外局番になるのです。
一方の「050型」は、電話番号が「050」で始まるタイプを指します。
スマートフォンでも導入可能であり、使い勝手のよさが大きな特徴です。
IP電話使用時の注意点
IP電話を使用するときは、一部の電話番号へ発信できないため注意しましょう。
たとえば、「110」「119」の緊急通報や「0120」のフリーダイヤルは、IP電話からは発信できません。
固定電話やスマホも所持していないと、万一の事態に遭遇したとき、不便に感じるでしょう。
また、インターネット回線を利用する関係から、接続状況によって通話時の音声品質が低下します。
一定の音声品質を確保するなら、プロバイダー選定から見直し、適切なネット環境を整備しましょう。
その上で、IP電話には番号ポータビリティが適用されません。
電話会社を変更すると、同じ電話番号を引き継いで利用できないため注意してください。
固定電話番号を取得した方がいい理由

プライバシー保護や銀行口座の開設などから、企業は固定電話番号を取得した方がいいとされます。
その理由について、複数の観点からご説明します。
プライバシー保護になる
法人が固定電話番号を取得することで、プライバシー保護になるといわれます。
第一に、法人名義で電話番号を取得すれば、個人名が表に出ることはありません。
個人情報の流出リスクを軽減でき、仕事とプライベートを明確に切りわけられるでしょう。
また、自社の固定電話番号があれば、会社の公式サイトや名刺に個人の携帯番号を記載する必要がなくなります。
代表や従業員の個人情報が外部に漏れるリスクを軽減できるのも魅力です。
クライアントから信用を得られる
仕事用に固定電話番号を取得すると、クライアントから社会的信用を得やすくなります。
昨今は通信技術が進歩し、ビジネスの場でさまざまな音声通話アプリやコミュニケーションツールが活用されるようになりました。
とはいえ、多くの法人や自治体は、以前と変わらず市外局番から始まる固定電話番号を利用しています。
そのような状況から、固定電話番号そのものが、社会的に「信頼される番号」という認識が広まっています。
IP電話や音声通話アプリの登場から、わざわざ固定電話番号を取得しなくても困らない時代になったのは確かです。
しかし、それらの電話番号を世間が信用しているかどうかは、別問題といえます。
個人事業主はともかく、一定の事業規模を誇る法人であれば、固定電話番号は取得しておくべきでしょう。
法人用の銀行口座を開設できる
法人用の銀行口座を開設する際、固定電話番号があると有利になります。
新しい会社を設立する際、通常は法人口座を用意するものです。
ただし、一般的な金融機関では、法人口座を開設するときに固定電話番号の入力を求めます。
自社の固定電話番号を取得していないと、法人口座開設の申し込みは受け付けてもらえないでしょう。
また、固定電話番号がないと、金融機関の融資が受けにくい傾向にあるため、注意が必要です。
登記情報を変更する手間が減る
固定電話番号を取得すると、電話番号が変わることが少ないため、登記情報の変更の手間や費用を軽減できます。
会社設立時に携帯電話番号を登記しておくと、後に固定電話番号を取得した際には登記情報を変更する必要があるものです。
変更登記には時間・手間がかかり、登録免許税などの費用も発生します。
しかし、固定電話番号は変更することがほぼないため、それらの手間や費用がかかりません。
固定電話番号を取得する方法とは?
ここでは、固定電話番号を取得する一般的な方法や、近年のビジネスシーンで活用されている音声通話サービス・システムについて解説します。
NTTの加入電話
固定電話番号を取得するなら、NTTの加入電話と契約するのが一般的です。
固定電話番号を取得するときは、NTT東日本・西日本の公式サイトや電話窓口から申し来ましょう。
取得時に免許証やパスポートで身分を証明し、電話番号を申請するのが一般的です。
ただし、回線工事に費用や時間がかかります。
申し込みから利用可能になるまでは、相応の時間を要するため注意しましょう。
クラウドPBX
クラウドPBXは、インターネット回線を利用し、外線・内線の通信環境を構築するサービスです。
これまで、社内に物理的な「主装置(PBX)」を設置し、音声通信網を構築するのが一般的でした。
この場合、主装置の導入費用や運用コスト、保守・運用の専任人材などが必要となります。
一方のクラウドPBXは、クラウド上に主装置を設置・運用し、社内の音声通信網を構築する仕組みです。
機器の設置工事や保守が不要であり、従来のPBXに比べて導入ハードルや運用コストが低くなります。
内線・外線の発着信や転送を柔軟にコントロールしたり、複数の拠点間を内線化したりと、クラウドPBXの導入により、電話業務が効率化されるでしょう。
IP電話
IP電話は、インターネットプロトコルを利用して音声通信を行うサービスの総称です。
アナログ回線を用いた固定電話サービスとは異なり、距離に応じて通話料金が高くなったり、音声品質が低下したりはしません。
大がかりな工事は不要で、初期費用やランニングコストを抑えられるのも魅了です。
IP電話の番号は、同サービスを提供している事業者に申し込むことで取得できます。
Webサイトや電話窓口で契約し、所定の審査を通ればそのまま利用できるでしょう。
なお、IP電話の通話品質はインターネット環境に左右されます。
さらに「050番号」であることから、固定電話番号に比べると、社会的信用が得られにくい点に注意しましょう。
光IP電話
光IP電話は、光ファイバー回線を利用したIP電話サービスのことで、NTTが提供する「ひかり電話」が有名です。
音声データの送受信に光回線を用いることで、高音質かつ安定的な音声通話を可能にしました。
一般的なIP電話に比べ、基本料金や通話料金がリーズナブルであり、緊急通報や「0120」に発信できる点も魅力です。
光IP電話の番号は、NTTなどの光回線プロバイダーと契約すれば取得できます。
光回線の契約と同時に、光IP電話への加入を申し込みましょう。
なお、利用には光回線の導入が必須であり、地域によっては利用できない場合があります。
企業におけるクラウドPBXの導入メリット
ここでは、企業がクラウドPBXを導入するメリットや魅力を詳しく解説します。
外出中も会社番号で受発信できる
取引先などの電話を外出先から受発信できるのは、クラウドPBXを導入する大きなメリットです。
上記の通り、クラウドPBXは主装置をクラウド上に設置します。
インターネット環境さえあれば、出先であっても社内の音声通信網に入り、内線・外線を利用できるのです。
これにより、社員一人ひとりのスマートフォンを内線化できます。
外出中もインターネット接続すれば、代表番号で電話をかけたり、逆に電話を受けたりできるわけです。
クラウドPBXの導入によって、常にオフィスの固定電話で通話する必要がなくなります。
複数間拠点を内線化できる
クラウドPBXを導入すれば、本社と支社A、支社Bといった複数の拠点を内線化できます。
複数拠点を単一の通信網に組み込むことで、通話料金の節約や電話業務の効率化が期待できるでしょう。
また、クラウドPBXなら、複数の拠点間を繋ぐ場合に配線工事が必要ありません。
海外支社など、非常に距離のある拠点においても、同じ通信網に組み込めます。
台数やオフィスレイアウトを容易に変更できる
クラウドPBXなら、電話の設置台数やオフィスレイアウトの変更が容易です。
たとえば、自社の従業員が増えた場合、業務上の理由で内線電話を増やすことがあります。
気分一新のため、社内のレイアウトを変更する場合もあるでしょう。
その都度配線工事を行ったり、ケーブル類を移動させたりするのは手間です。
クラウドPBXは、内線・外線の増設などはすべて、システム上で処理できます。
大量のケーブルを社内に引っ張ることもないため、レイアウト変更もスムーズです。
BCP対策になる
クラウドPBXの導入は、BCP(事業継続計画)対策に非常に有効です。
日本は地震や台風などの自然災害が多いため、近年は企業におけるBCP対策の重要性が高まっています。
クラウドPBXを導入すれば、オフィスが停電しても、またはオフィス自体が被災した場合でも、業務を継続可能です。
シンプルかつ効果的なBCP対策となるため、コールセンターなどを運営する企業などで導入されています。
また、NTTコミュニケーションズでもクラウドPBXサービスを提供しており、スマートフォンの内線化によるBCP対策モデルや導入事例を紹介しています。
オフィスが被災してもインターネット環境があれば稼働できる、「災害に強い業務体制」の構築にクラウドPBXは欠かせません。
まとめ
デジタル社会の現代においても、多くの企業ではアナログ回線の固定電話が利用されています。
さらに業務効率化やBPC対策の観点から、クラウドPBXの導入も進んでいるのです。
内線・外線の発着信や転送のコントロール、複数拠点間の内線化など、自社の電話システムを見直したい方は、クラウドPBXの導入を検討してみましょう。
スターティアでは、クラウドPBXや多機能ビジネスフォンの導入支援を行っております。
機種選定から導入・保守、障害発生時のトラブル対応まで、お客様に寄り添ったサービスを提供しています。
これからクラウドPBXや多機能ビジネスフォンの導入を検討される方は、ぜひ一度当社までお問い合わせください。
▽スターティアのサービス▽
▽関連サービス▽
▽関連サービス2▽
▽関連記事▽
電話回線の豆知識|種類と特徴、申し込みから工事までの流れを解説
ビジネスフォンの主装置とは?価格や耐用年数、クラウドPBXについても解説!
おすすめ資料ランキング
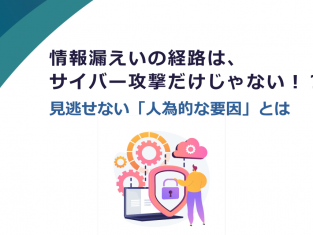
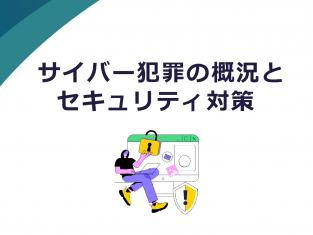



【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-