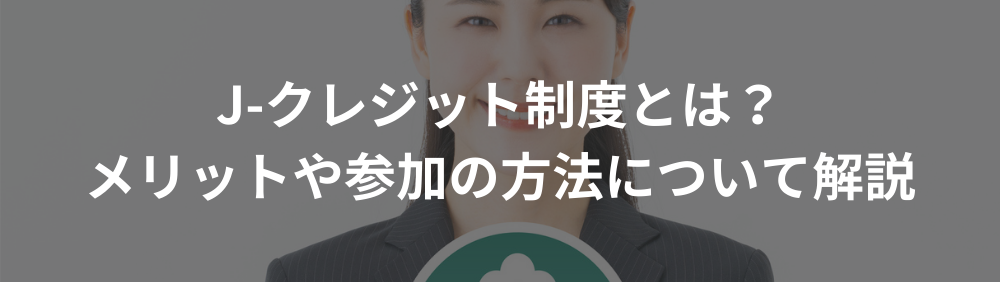
J-クレジット制度についてご存知でしょうか? 「ビジネスを省エネ化したい」「企業として地球温暖化対策に貢献したい」と考えている企業様には知っておいていただきたい制度です。
こちらでは、J-クレジット制度の概要や参加の方法について解説します。
J-クレジット制度とは
J-クレジット制度とは、CO2をはじめとする温室効果ガスの削減量を、国が「クレジット」として認証する制度のことです。
前身となったのは、経済産業省が主導していた「国内クレジット制度」と環境省が主導していた「オフセット・クレジット制度」です。
2013年にこの2つの制度が統合され、現在のJ-クレジット制度が生まれました。
なお、J-クレジット制度は現在のところ、2030年までの制度です。
2030年以降の予定についてはまだ決まっていません。
J-クレジット制度の目的
J-クレジット制度の主な目的は、温室効果ガス排出量の削減です。
温室効果ガス排出量の増加、ならびに、それにともなう地球温暖化は、世界が直面している問題のひとつです。
各国が温室効果ガス削減に向けた取り組みを行っており、こうした世界の動きに足並みを揃えるため、日本はJ-クレジット制度を開始しました。
また、経済の流れを生むという目的もあります。
J-クレジット制度は、温室効果ガスの削減量をクレジットとして発行し、可視化する制度です。
発行したクレジットは、他の企業によって買い取られます。
このように、CO2削減効果と同時に資金循環を促進するのも、J-クレジット制度の目的のひとつです。
J-クレジット制度に関連する機関・企業と役割
J-クレジット制度における取引には、管理者となる国、J-クレジットの創出者と購入者、プロバイダーが関係しています。
以下では、J-クレジット制度におけるそれぞれの役割について解説します。
J-クレジットの管理者となる国
J-クレジットは、国によって管理されている制度です。
具体的には、経済産業省、環境省、農林水産省が「制度管理者」として設定されています。
このほか、運営委員会、認証委員会、審査期間があり、それぞれが連携して制度の運営を行っています。
J-クレジット創出者となる企業・機関
温室効果ガスの削減に貢献し、クレジットを発行している企業・機関は、創出者としての役割を担います。
国に温室効果ガス排出・吸収事業として認められれば、業種は問われません。
実際に、さまざまな業種の企業が創出者としてJ-クレジット制度に参加しています。
また、民間の企業だけではなく、森林所有者や自治体の創出者も少なくありません。
J-クレジット購入者となる企業・機関
創出者が発行したクレジットを購入する企業・機関は、購入者としての役割を担います。
購入者は、自らが温室効果ガスを削減していくのが難しい場合も、省エネ活動に貢献できます。
J-クレジットの創出・活用を支援するプロバイダー
プロバイダーとは、創出者のクレジット発行を支援する事業者のこと。
J-クレジット制度において国による正式な認可を受けたプロバイダーは、「J-クレジット-プロバイダー」と呼ばれます。
J-クレジット制度によるメリット
J-クレジット制度は、創出者と購入者のそれぞれにとってメリットがある制度です。
以下では、それぞれの立場からのメリットを解説します。
J-クレジット創出者のメリット
J-クレジット創出者にとっては、以下のようなメリットがあります。
省エネ設備・再生可能エネルギーの導入でランニングコストが減る
クレジットを発行するためには、省エネ設備や再生可能エネルギーの導入が必要です。
これらの導入によりランニングコストが減る点は、創出者にとってのメリットのひとつ。
導入のために初期コストがかかりますが、長期的に考えれば、コスト削減効果でカバーできます。
クレジットを売却すると利益になる
発行したクレジットを他事業者に買い取ってもらえた場合は、売却益を得られます。
省エネに投資した費用を回収したり、さらなる投資に回したりする使い方が一般的です。
地球温暖化に取り組んでいることを対外的にアピールできる
クレジットを創出していることを体外的にアピールすることで、「温暖化対策に取り組んでいる企業」というイメージを打ち出すことができます。
同じように環境問題に貢献したいと考えている消費者や法人からの支援が期待できるでしょう。
クレジットを活用する企業・機関とのネットワークを構築できる
クレジットを活用する企業・機関と、新しいコネクションが生まれるケースがあります。
実際に、クレジットの取引がきっかけとなりビジネスチャンスにつながった例もございます。
組織内に省エネに取り組む意識が根付く
制度に参加していることを社内に周知することで、近年環境問題に興味を持つ方も増えているため、対外だけでなく社内へのアピールや、省エネに対する意識付けにも繋がります。
J-クレジット購入者のメリット
J-クレジット購入者にとっては、以下のような点がメリットです。
創出者の省エネ活動を後押しできる
クレジットを買い取ることで、創出者の省エネ活動を後押しできます。
自社が温室効果ガスを削減できないとしても、間接的に環境問題に貢献することが可能です。
省エネに取り組んでいる企業として評価が高まる
クレジット購入を体外的にアピールすることで、省エネに取り組んでいる企業としての評価アップが期待できます。
プレスリリースや企業調査などで、J-クレジット制度への参加を積極的に発表することがポイントです。
CO2排出量をオフセットすることで競合との差別化ができる
クレジット購入によって、商材の生産・販売工程に係るCO2排出量をオフセットできます。
商品・サービスに付加価値が生まれるため、競合との差別化が可能です。
クレジットの購入を通じてネットワークが広がる
クレジットの購入によって、他事業者とのネットワークが広がります。
創出者との関係性が強まれば、双方の強みを生かした新事業を打ち出すことも可能です。
日本の環境へのメリット
日本の環境には、以下のようなメリットがあります。
温室効果ガスの排出量が削減される
創出者にとっては、温室効果ガスの削減がそのまま利益につながります。
参加企業が増えていけば、日本全体における温室効果ガスの排出量が削減されるでしょう。
クレジットの売買による経済効果が生まれる
クレジットが取引されることにより、経済効果の活発化が期待できます。
売却益を獲得した創出者が省エネに追加投資を行えば、日本全体の省エネ事業の成長につながるでしょう。
「環境に配慮している国」として国外にアピールできる
J-クレジット制度の取り組みが一般的になれば、「環境に配慮している国」として、世界中にアピールできるでしょう。
将来的には、日本がCO2排出量問題を牽引する立場のなることも考えられます。
J-クレジット購入者が制度に参加する方法・流れ
J-クレジット制度に購入者として参加したい場合は、以下のような方法があります。
- J-クレジット・プロバイダーに相談する
- 「売り出しクレジット一覧」のクレジットを購入する
- 入札制度を利用する
J-クレジット・プロバイダーは、創出者と購入者を仲介する存在です。
クレジットの購入のほか、カーボン・オフセットに関するアドバイスも受けられます。
「売り出しクレジット一覧」は環境省が公開している、売り出し中クレジットの検索サービスです。
地域やプロジェクト種別でクレジットを検索できます。
J-クレジット制度事務局が実施している入札制度でクレジットを購入することも可能です。入札販売は、1年に1~2回実施されています。
クレジットの購入を希望している場合は、上記の方法を検討してみましょう。
J-クレジット制度の課題
J-クレジット制度は、日本のCO2排出量削減につながることが期待されている制度です。
一方で、いくつかの課題も指摘されています。
代表的な問題が、登録までに時間がかかる点です。
創出者として登録されるまでには、相談・報告書の作成・審査など多くの工程を通過する必要があり、一般的には5カ月ほどかかります。
この手続きの煩雑さが、J-クレジット制度の普及を妨げている点は否定できません。
創出者にとってのメリットが実感しにくい点も課題です。
申請の準備からクレジットの売却益が還元されるまでには、約4年という長い年月を要します。
また、プロジェクトの負担に対して発行されるクレジットの量が少なく、利益を得る方法としては効率が悪い点も事実です。
また、購入者にも環境問題に取り組む意識が必要です。
オフセットの仕組みがあることから、「お金を出せばCO2を排出しても問題ない」という無責任な取り組みになってしまう傾向があります。
まず、自社で排出量の削減に取り組んだうえで、どうしても削減できない部分をオフセットする、という意識が大切です。
このように、現状は創出者にとって負担となる点が数多く指摘されており、今後はこれらの課題を少しずつ解消していく必要があります。
しかし、J-クレジット制度によってCO2排出量の削減効果が現れているのは事実です。
認証されているクレジットの量は年々増加しています。
特に、資金力が乏しい企業でも温室効果ガスの削減に取り組めることから、中小企業や地方自治体の参加例が目立っているようです。
まとめ
J-クレジット制度について解説しました。
現状は、問題点も残されていますが、省エネに投資している企業や環境問題に取り組みたい企業にとっては参加しやすい制度と言えます。
また、事業の性質上、CO2排出量の削減が難しい企業でも参加できる点は魅力であり、企業イメージの向上、商材の差別化など、購入することによる副次的なメリットもあります。
環境問題に何かしらの形でコミットしたい場合は、J-クレジット制度への参加を検討してみてはいかがでしょうか。
スターティアでは、環境クレジット付き「カーボンオフセットプラン」を提供しています。
また、より詳しく情報を知りたい方向けにホワイトペーパー(カーボンオフセット)をご用意しております。
ご興味がある企業様はお気軽にご相談ください。
おすすめ資料ランキング





【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-





















