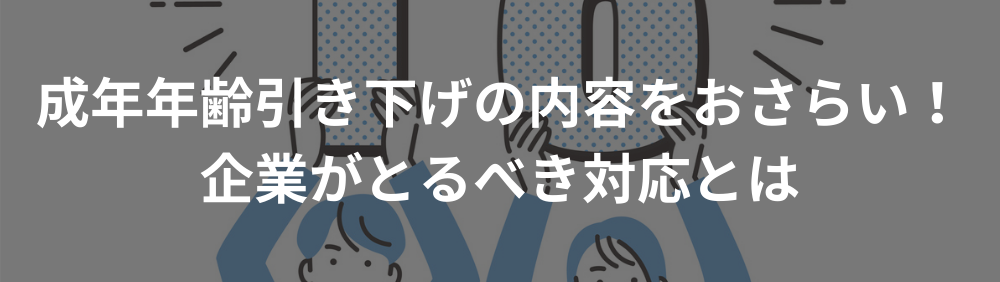
2022年4月1日、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。
多くの事業者は、業務フローや人事などに影響を受けます。
この改正によってどのような対応を自社がしなければいけないのか、あらかじめ把握しておきましょう。
この記事では、今回の成年年齢引き下げの概要や、事業者側に求められる対応について解説します。
民法改正による成年年齢引き下げについておさらい
まずは、旧民法において成年・未成年がどのように定義されていたのか、今回の民法の改正によって成年の定義がどのように変わるのかおさらいしておきましょう。
旧民法における成年・未成年の定義
旧民法の第4条では、「年齢二十歳をもって、成年とする」と定められていました。
つまり、20歳で成年を迎え、それまでは未成年ということです。
未成年者は、経験・知識・判断能力の不足が懸念されます。
そのため、未成年保護の観点から、責任をともなう法律行為には法定代理人の支援が必要です。
本人が自分の意思で自由に法律行為をするためには、20歳になるのを待つ必要がありました。
具体的には、契約の締結などは未成年者だけで行うことはできません。
民法によって成年年齢が定められたのは明治29年(1896年)のことです。
今回、約130年ぶりに成年年齢の見直しが行われ、18歳に引き下げられることになりました。
成年年齢引き下げの背景
今回の成年年齢引き下げは、若い世代をより社会活動に参加させるためだと考えられています。
2015年には、若い世代も「社会の担い手」として国を左右する重要な決断に参加させるため、選挙権年齢を18以上に引き下げる法改正が行われました。
これ以降、18、19歳を大人として扱い、政治的な判断に参加させる動きが加速しており、今回の成年年齢引き下げもそうした流れが背景にあります。
また、世界的に見ても18歳から成年として扱う国が多数派です。
そのため、グローバルスタンダードに足並みを揃えるための改正とも言えます。
未成年が成人となるタイミング
成年年齢引き下げは2022年4月1日に施行されています。
未成年者が成人するタイミングは、生年月日によって異なります。
改正前に未成年者だった人は、以下のタイミングで成人となります。
| 生年月日 | 成人となるタイミング |
|---|---|
| 2002年4月2日~2004年4月1日 | 2022年4月1日 |
| 2004年4月2日以降 | 18歳の誕生日 |
成人になるとできること
成人を迎えると、以下のことができるようになります。
個人の判断による契約の締結
18歳(成人)になった時点で、単独での契約手続きができるようになります。
例として、以下のような契約は親の同意なしで締結できるようになります。
- 携帯電話の契約
- ローン契約
- クレジットカードの契約
- 賃貸契約
親権からの離脱により可能になること
成人にともない親権から離脱するため、いくつかの判断・決断を本人だけで下せるようになります。
以下が具体例です。
- 居住地の選択
- 職業の選択
- 財産の管理・処分
10年有効パスポートの取得
パスポートには5年有効のものと10年有効のものがあります。
未成年者は10年有効パスポートの発給を申請できません。
成年年齢の引き下げ前は、20歳になるまで10年パスポートを取得できませんでした。
しかし現在では、引き下げにともない、18、19歳の人でも10年パスポートを取得可能になっています。
一部国家資格の取得
公認会計士・行政書士・司法書士・社会保険労務士などの国家資格や医師免許は、未成年者には取得できません。
そのため、以前は20歳にならなければ取得できませんでしたが、成人年齢の引き下げにより18、19歳でも取得できるようになっています。
ただし、一定期間の実務経験や大学の正規課程修了が求められる資格もあります。
現実的にこうした資格を18歳で取得することは困難です。
性別変更審判の申し立て
戸籍上の性別を変更する性別変更審判の申し立ては、未成年には認められていません。
成人年齢の引き下げにより、18、19歳でも性別変更審判を申し立てられるようになります。
成人になっても引き続き許可されないこと
18、19歳の人が成年として扱われることになりますが、これまで20歳に人に許可されていたことがすべて解禁されるわけではありません。
健康問題やその他トラブルにつながるリスクから、以下のようなことは引き続き20歳になるまで待つ必要があります。
飲酒・喫煙
飲酒・喫煙は健康に与える悪影響から、引き続き20歳まで禁止されることになりました。
ギャンブル
競馬や競輪、オートレースなどのギャンブルは、引き続き20歳になるまで禁止です。
これは、ギャンブル依存症対策などの観点から講じられた措置です。
養子縁組
成年年齢引き下げ後も、20歳以上になるまで養親になることはできません。
大型・中型自動車免許の取得
大型・中型自動車免許の取得には、それぞれ以下のような要件が定められていました。
- 大型免許:21歳以上、普通免許の保有歴3年以上
- 中型免許:20歳以上、普通免許の保有歴2年以上
これらの要件は、成年年齢引き下げの影響を受けません。
ただし、2022年5月13日からは改正道路交通法が施行されています。
大型・中型自動車免許の受験資格は、一律で以下のように変更されました。
- 19歳以上、普通免許等の保有歴1年以上
新成人にとってのメリット・デメリット
成年年齢の引き下げによって18、19歳の人は好影響と悪影響の両方を受けることになります。
新成人にとってのメリット・デメリットを解説します。
メリット
代表的なメリットは、自分の独断で決められることが増える点です。
クレジットカードや携帯電話の契約の際に、親の同意が求められることはありません。
また、居住地や仕事を自分で決められるため、人生設計の自由度も広がります。
一部の国家資格の受験要件も満たせるため、若年層のうちから将来に有益な資格の取得に挑戦できるようになりました。
デメリット
18、19歳の新成人に未成年者取消権が適用されなくなるため、契約トラブルの増加が懸念されています。
未成年者取消権とは、親の同意を得ずに締結した契約を取り消せる権利のことです。
未成年者はこの権利によって契約トラブルから保護されています。
2022年4月1日以降、18、19歳が締結した契約には、この未成年者取消権が適用されません。
この変更に乗じて、18、19歳の新成人に不当な契約を迫る悪徳業者が横行することが見込まれます。
政府は、新成人に対して、軽率に契約を締結しないように注意することを呼びかけています。
成年年齢の引き下げで企業がとるべき対応
今回の成年年齢引き下げにともない、企業はどんな対応をとるべきなのでしょうか。
以下では、企業に求められる具体的な対応を解説します。
利用規約・約款の変更
顧客に提示している利用規約や約款に20歳を成年年齢として定義している内容があれば、必要に応じて変更しなければなりません。
例として、「20歳未満の方は、契約の締結に際して法定代理人の同意が必要です」といった記載がある場合は、変更が求められます。
Web、紙資料、メールなど、各媒体での記載内容をくまなくチェックしましょう。
システムに登録されている情報のステータス変更
サービスの利用に関して未成年者の登録を制限している場合もあるでしょう。
2022年4月1以降、18、19歳は未成年としては扱われないため、システム改修を行う必要があります。
また、既存のユーザー情報に対するステータス変更も必要です。
未成年であるという理由から利用できるユーザーを限定しているサービスがある場合は、18、19歳も利用できるようにシステムを刷新しなければなりません。
システムの改修にはエラーが起きる可能性があるため、慎重に実施する必要があります。
また、該当ユーザーにはメールなどで周知することが求められます。
契約フローの見直し
18、19歳でも法定代理人の同意なしで契約を締結できるようになります。
20歳未満の契約希望者に対して、法定代理人の同意を求めていた場合は、契約フローを見直しましょう。
例として、以下のような契約ではフローを見直す必要があります。
- 携帯電話の契約
- アパート・マンションの賃貸借契約
- クレジットカードの契約
- 自動車ローンの契約
従業員への情報共有
店舗などで対面接客を行っている場合は、今回の成年年齢引き下げに関して従業員に情報共有しておくことも必要です。
単に「18、19歳を成人として扱う」と指示するだけではなく、18、19歳に許可されていないことについても周知しておくことが求められます。
例として、成年年齢が下げられても、喫煙や飲酒は引き続き18、19歳には許可されていません。
そのため、タバコや酒類を18、19歳に提供することはできません。
競馬・競輪・オートレースなどギャンブルの投票券も、顧客が20歳以上であることを確認したうえで提供しなければなりません。
施行後しばらくは、現場の混乱が予想されます。
万が一トラブルが起きた際は事業者の責任が追及されることも考えられるため、情報周知を徹底しましょう。
18、19歳の従業員に対する対応変更
現行の労働基準法では、18歳以上の労働者に対する制限などはありません。
そのため、18、19歳の従業員を雇用している事業者であっても、今回の成年年齢引き下げによる影響はないと考えられます。
一方、18、19歳の採用時に法定代理人の同意を求めることは必須ではなくなりました。
今後、親の同意を求めるかどうかは、事業者側の裁量に委ねられています。
トラブルを避けるために引き続き親の同意を求めても問題ありません。
親の同意を必須にするのではなく、親に身元保証人になってもらうという選択肢もあります。
まとめ
成年年齢の引き下げについて解説しました。
若い世代をターゲットにした事業を行っている場合は、少なくとも影響を受けることになるでしょう。
また、従業員として18、19歳を雇用している場合も必要な対応について検討してください。
おすすめ資料ランキング





【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-





















