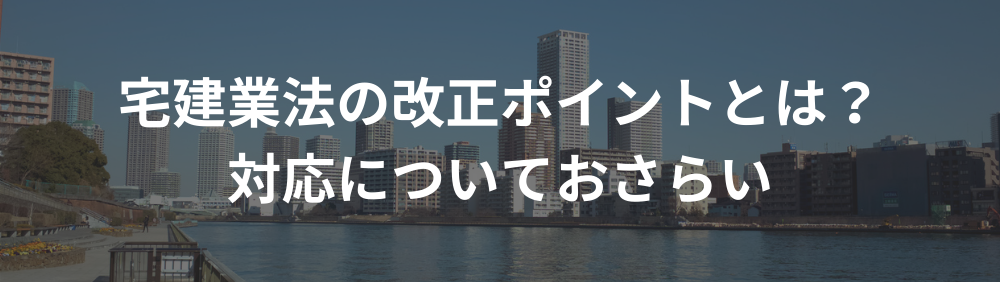
2022年5月18日より、改正された宅建業法が施行されています。
今回の改正では、デジタル改革関連法案の内容を反映した変更が加えられました。
効率的な契約が可能になるため、不動産関連の事業者の方はしっかりと改正内容を把握しておきましょう。
この記事では、今回の宅建業法の改正ポイントについて解説します。
宅建業法とは
宅建業法とは、正式には「宅地見物取引業法」という法律です。
1952年に、宅地・建物の取引を規制するルールとして制定されました。
流通の円滑化を目的として、宅地見物取引業者の免許制度などを規定しています。
最重要視されているのは、宅地・建物を購入する人の利益保護です。
開業手続、業務、取引主任者について規制を設けているほか、違反者に対するペナルティを設定しています。
宅建業法により、不動産業界の事業者は一般消費者に対して一方な取引を押し付けることはできません。
不動産業界をクリーンに保つために、重要な役割を担っている法律です。
2021年交付・2022年施行の改正の背景
2022年5月施行の今回の宅建業法改正は、「デジタル改革関連法案」整備の一環です。
「デジタル改革関連法案」とは、以下の法律の総称です。
- デジタル庁設置法
- デジタル社会形成基本法
- デジタル社会形成整備法
- 公金受取口座登録法
- 預貯金口座管理法
- 自治体システム標準化法
いずれの法律も、国や民間事業者のデータ利活用を促進するために制定された法律です。
現在は、国、民間を問わずデータを効率的に処理することが求められています。
一方で、現行の法律がデータの円滑な処理を妨げてしまうケースは少なくありません。
とりわけ、近年は新型コロナウイルス感染拡大により、損害をカバーするための給付金対応の遅れ、マイナンバーの申請の不備など、社会全体のデジタル化が不十分であることによる問題が散見されました。
デジタル改革関連法案は、こうした背景から社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための法案です。
不動産業界では、2019年10月から書面を電子化する社会実験を行っています。
この実験によって目立ったトラブルが確認されなかったことから、今回の改正が踏み切られることになりました。
宅建業法の改正内容
今回の宅建業法の改正は、2021年5月に施行開始された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の流れを受けています。
この法律は、手続における押印の廃止、手続の電子化について定めたものです。
この法律の一環として、2022年5月から宅建業法では以下のような改正内容が施行されています。
押印の廃止
今回の改正により、以下の書類の押印が不要になっています。
- 重要事項説明書
- 宅地・建物の売買・交換・賃貸契約締結時の交付文書
「重要事項説明書」は、権利関係、整備状況、取引条件など、物件に関して最低限説明が必要な事項について記載された書類のことです。
宅地建物取引士から、取引の相手に対して交付されます。
改正前は宅地建物取引士の記名・押印が必要でしたが、改正により押印が不要になり、記名のみで効力が認められることになりました。
「宅地・建物の売買・交換・賃貸契約締結時の交付文書」は、代金や賃料、支払方法などが記載された書類のことであり、一般的には「37条書面」と呼ばれています。
こちらも、改正以降は押印が不要になりました。
電磁的な書面交付の認可
上記の社会実験によって大きな問題が起こらなかったことから、改正後は以下の書面の電磁的な交付が認められています。
- 媒介契約・代理契約締結時の交付書面
- レインズ登録時の交付書面
- 重要事項説明書
- 37条書面
旧法では、一部の媒介契約・代理契約において、書面交付が義務付けられていました。
改正後、電磁発行された媒介・代理契約書面が認められています。
レインズとは、所在規模、形質、価値などの物件情報を登録する指定流通機構のこと。
不動産業者は、専任媒介契約を締結した際に物件情報をレインズに登録したうえで、さらに登録の事実を証明する書面を発行しなければなりません。
この書面について、改正後は電磁的な発行が認められることになりました。
重要事項説明書、37条書面についても電磁的な発行が認められています。
宅建業法改正の注意点
今回の改正により、不動産業者にとっても顧客にとってもさらに負担の少ない取引が実現されています。
一方で、すべての押印や紙資料が不要になっているわけではありません。
以下のような点に注意しましょう。
媒介書面への押印は必要
今回の改正では、媒介契約書面(34条の2の書面)の押印に関する内容は変更されていません。
したがって、媒介位契約書面には引き続き宅地建物取引業者の押印が求められます。
従業員証明書の携帯自体は必要
今回の改正に先駆けて、2021年9月1日から従業員証明書の押印が不要になっています。
従業員証明書とは、宅地建物取引業者が、従業員であることを証明するためスタッフに発行する書類のことです。
取引者から請求された場合に備えて、不動産業者の従業員はこの書類を携帯していなければなりません。
今回の改正においても、この書面の携帯義務自体はなくなっていません。
あくまで不要になったのは、押印のみです。
国交省が提供しているマニュアルのポイント
国交省は不動産業界のDX化のため、宅地建物取引業者に対してマニュアルを提供しています。
(参照:重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル)
以下では、このマニュアルに関しておさえておくべきポイントを紹介します。
相手のIT環境を事前に確認しておく
宅建業法の改正により、書面の電磁発行が認められています。
しかし、電磁発行は書類の提出先にとって望ましいとは限りません。
書面を受け取るための端末の有無、また相手のITリテラシーによっては、電磁化された書面を相手が確認できない場合があります。
国交省のマニュアルでは、書面を電磁的に発行する前に、相手のIT環境を確認する必要があることを定めています。
相手が対応できない場合は、問題をクリアにしてから電磁的な書面を発行するか、紙資料の提供に切り替えなければなりません。
書面の電子化に関する要件を確認しておく
マニュアルでは、書面の電子化に対して以下の要件を定めています。
- 相手方が出力することで、書面を作成できる
- 電子化された書面が改変されていないことを証明できる措置を講じている
特に、「書面が作成されて以降、改変されていないこと」については、相手にしっかりと理解してもらわなければなりません。
書面を作成した際の通知方法について確認しておく
マニュアルには、書面を電子化する方法について限定するような記載はありません。
ただし、加工・処理させることを想定して、視認性を確保することは重要です。
ファイル形式を変換した際などに、文字化けやぼやけなどが発生しないような対策を講じる必要があります。
相手が契約者本人であることを確認する
不動産の売買取引では、マネーロンダリングを防止しなければなりません。
このことから、契約当事者本人、もしくは代理人であることの確認を徹底することが、犯罪収益移転防止法によって定められています。
書面の電子化による不動産業者にとってのメリット
書面を電子化することによって、不動産業者はどのようなメリットを享受できるのでしょうか。
以下では、正面の電子化による具体的なメリットを解説します。
印紙税のコスト削減
不動産の売買契約を書面で締結する場合、取引金額に応じた印紙税の支払が必要です。
書面には、印紙税の金額の収入印紙を貼り付けます。
印紙税の額は、取引金額に応じて大きくなります。
高額の取引が多い不動産売買では、印紙税による負担が大きくなりがちです。
電磁的な書面で契約を行う場合、印紙税の支払義務は発生しません。
したがって、書面を電子化することにより、印紙税のコスト削減につながります。
取引の効率化
契約を電磁的な書面で行うことによって、取引の効率化が期待できます。
特に、遠隔地に所在している不動産に関する契約では、書面のやり取りによってスピーディーな取引が妨げられてしまうケースが少なくありません。
また、近年は新型コロナウイルスの影響により、対面せず締結する契約のニーズが高まっています。
電磁的な書面による契約であれば、距離が問題になることはなく、非対面でも締結できます。
近年は、ビデオ会議ツールなどで顧客と宅建業者が打ち合わせを行い、そのまま電磁的な書面で契約に移行するようなケースも一般的です。
書類保管コストの削減
不動産の契約で発行された書面は、いつでも確認できるように保管しておかなければなりません。
紙の書面で契約を行っている場合、保管スペースの確保が問題になります。
契約件数が多い不動産業者であれば、事業所内に専用のスペースを確保しておかなければなりません。
また、確認が必要になるタイミングのことを考えて、ファイリングしておく手間もかかります。
書面を電子化しておけば、こうした物理的な書面の保管スペースは必要ありません。
さらに、各ファイルに契約締結日、契約者氏名などのデータが組み込まれていることから、検索性も大きく向上します。
総じて、書類の保管コスト・管理コストが大幅に低減される点は、書面の電子化による大きなメリットです。
まとめ
2022年の5月から施行されている宅建業法の改正内容について解説しました。
多くの書類で押印が不要になったほか、電子的な書面発行が可能となっています。
この改正に伴い、媒介・代理契約の締結から売買・賃貸契約まですべての契約において、電子的な方法で行うことが可能となっています。
今後、不動産業界の紙離れは急速に進んでいく見込みです。
不動産事業者にとって、契約の電子化は業務の効率化につながります。
また、遠隔地の契約が可能になる点や対面の打ち合わせが不要になる点など、顧客側のメリットも少なくありません。
宅建業者であれば、契約書面の電子化を積極的に進めましょう。
おすすめ資料ランキング





【著者・監修者企業】
弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。
資格
一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号
古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号
労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331
小売電気事業者 経済産業省登録:A0689
電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266
媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391
関連SNS
- トータルサポート
-
-
- オフィス環境
-
-
- 目的別で探す
- ネットワーク環境
-
-
- 環境サービス
-
-
- 目的別で探す
- Webプロモーション
-
-
- 3Dソリューション
-
-





















